経歴
-
2014年-
早稲田大学法学学術院教授(現在に至る)
-
2005年-2014年
九州大学大学院法学研究院教授
-
2009年-2010年
ニューヨーク大学ロースクール・フェロー(フルブライト・スカラー)(22年10月まで)
-
2009年
デューク大学客員教授
-
2009年
シンガポール大学客員教授
-
2007年
ミュンヘン大学客員教授
-
2003年-2004年
九州大学大学院法学研究院助教授
-
1997年-2003年
滋賀大学経済学部(法システム講座)助教授
-
1999年-2000年
ハーバード大学ロースクール客員研究員(12年8月まで)
-
1998年-1999年
カリフォルニア大学バークレイ校ロースクール客員研究員(11年8月まで)
-
1995年-1997年
滋賀大学経済学部(法システム講座)専任講師
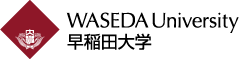

Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API in March 02, 2026, via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .