経歴
-
2002年04月-2024年03月
早稲田大学大学院日本語教育研究科 Professor
-
1999年-2002年
宮城教育大学 教授
-
1993年-1999年
宮城教育大学 助教授
2026/02/16 更新
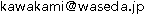
早稲田大学大学院日本語教育研究科 Professor
宮城教育大学 教授
宮城教育大学 助教授
大阪大学 大学院文学研究科 博士課程 日本学
大阪外国語大学 大学院外国語学研究科 東アジア語学専攻
大阪外国語大学 外国語学部 モンゴル語
日本社会学会
日本語教育学会
日本文化人類学会
文化人類学,日本語教育, 「移動する子ども」学
サー・ニール・カリー奨学金出版助成
2010年 豪日交流基金 移民の子どもたちの言語教育ーオーストラリアの英語学校で学ぶ子どもたち
「目黒モデル」と JSL バンドスケール─年少者日本語教育の専門家をどのように養成するか─
川上郁雄
早稲田日本語教育学 ( 38 ) 51 - 60 2025年06月
担当区分:筆頭著者
「JSL バンドスケール」は子どもの日本語教育を担う指導者の実践力向上に役立つのか
川上郁雄, 塩田紀子
早稲田日本語教育学 ( 37 ) 127 - 136 2024年12月
担当区分:筆頭著者
書評 モバイル・ライブズの青春群像 ― 岩城けい(2023)『M』集英社
川上郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」―ことばの教育を創発する ( 15 ) 92 - 97 2024年11月 [査読有り]
担当区分:筆頭著者
記号接地問題と「移動する子ども」学
川上郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」―ことばの教育を創発する ( 15 ) 56 - 79 2024年11月 [査読有り]
担当区分:筆頭著者
情動の視点から見る「移動する子ども」学
川上郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」ーことばの実践を創発する ( 14 ) 66 - 80 2023年11月 [査読有り]
担当区分:筆頭著者
未来へ繋ぐ日本語教育ー「移動する子ども」という経験と記憶の視点から
川上郁雄
24 1 - 21 2023年08月 [招待有り]
担当区分:筆頭著者
「移動する子ども」学から「継承語教育」を考える
川上郁雄
日本語学研究 ( 75 ) 31 - 49 2023年03月 [招待有り]
担当区分:筆頭著者
川上, 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 13 1 - 3 2022年11月
細川, 英雄, 川上, 郁雄, 蒲谷, 宏
早稲田日本語教育学 31 1 - 14 2021年12月
川上, 郁雄, 石井, 恵理子, 池上, 摩希子
早稲田日本語教育学 30 1 - 15 2021年06月
川上, 郁雄
早稲田日本語教育学 30 17 - 21 2021年06月
緒言 : 日研設立20周年記念特集として—特集 子どもと日本語教育 : 専門家の養成・研修のあり方を実践から考える
川上 郁雄
早稲田日本語教育学 = Waseda studies in Japanese language education ( 30 ) 1 - 4 2021年06月
書評 岩城けいの世界を読む 『ジャパン・トリップ』(角川書店,2017),『Matt』(集英社,2018)
川上, 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 11 100 - 113 2020年12月
「移動する子ども」というフィールド—特集 人文社会科学の四半世紀を振り返る ; 変わりゆく社会を追って
川上 郁雄
比較日本文化研究 = Journal of comparative studies in Japanese culture ( 20 ) 19 - 31 2020年10月
川上, 郁雄, 三宅, 和子, 岩﨑, 典子, タスタンベコワ, クアニシ, 下地, ローレンス吉孝, チャップマン, デビッド
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 10 46 - 72 2019年07月
「移動する子ども」という記憶と社会
川上郁雄
文化を映す鏡を磨く 15 - 34 2018年07月 [査読有り]
書評 モバイル・ライブズを生きる「移動する家族」の物語 岩城けい(2017)『Masato』集英社文庫
川上, 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 9 40 - 46 2018年06月
川上, 郁雄
多文化社会研究 = Journal of Global Humanities and Social Sciences, Nagasaki University 4 73 - 91 2018年03月
川上, 郁雄
早稲田日本語教育学 23 109 - 110 2017年12月
論文 「移動する子ども」をめぐる研究主題とは何か 複数言語環境で成長する子どもと親の記憶と語りから
川上, 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 8 1 - 19 2017年06月
書評 小説に昇華した「移動する子ども」という記憶 温又柔(2016).『来福の家』白水社(U ブックス).
川上, 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 8 29 - 32 2017年06月
「移動する子ども」をめぐる研究主題とは何かー複数言語環境で成長する子どもと親の記憶と語りから
川上郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」-ことばの教育を創発する 1 - 19 2017年05月 [査読有り]
「移動する子ども」をめぐる研究主題とは何かー複数言語環境で成長する子どもと親の記憶と語りから
川上 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」ーことばの教育を創発する 8 1 - 19 2017年 [査読有り]
第38回研究大会ワークショップ 国際移動する日本語使用者の言語実践とアイデンティティ
三宅 和子, 川上 郁雄, 岩﨑 典子, 平高 史也
社会言語科学 19 ( 2 ) 98 - 103 2017年
川上, 郁雄
早稲田日本語教育学 20 i - ii 2016年06月
川上 郁雄
早稲田日本語教育学 = Waseda studies in Japanese language education ( 20 ) 33 - 47 2016年06月
書評 我住在日語:わたしは日本語に住んでいます。 温又柔(2016).『台湾生まれ 日本語育ち』白水社.
川上, 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 7 59 - 69 2016年06月
ベトナム系日本人ー「名づけること」と「名乗ること」あいだで
川上郁雄
マルチ・エスニック・ジャパニーズー〇〇系日本人の変革力 168 - 184 2016年05月 [招待有り]
「ことばの力」とは何かという課題
川上郁雄
日本語学 ( 10月号 ) 56 - 64 2015年10月 [招待有り]
あなたはライフストーリーで何を語るのか
川上郁雄
日本語教育学としてのライフストーリーー語りを聞き、書くということ 24 - 49 2015年10月
宮崎, 里司, 川上, 郁雄
早稲田日本語教育学 17-18 1 - 8 2015年02月 [査読有り]
「難民」として来日した親を持つ子どもたちの記憶と自己表象ー複言語と無国籍の間で
比較日本文化研究 ( 17号 ) 48 - 70 2014年12月 [査読有り]
ことばとアイデンティティー複数言語環境で成長する子どもたちの生を考える
川上郁雄
日本に住む多文化の子どもと教育 117 - 144 2014年01月 [招待有り]
書評 「移動する子ども」の壮大な家族史 一青妙(著)『私の箱子』講談社,2012年
川上, 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 3 121 - 127 2012年05月
「移動する子どもたち」は大学で日本語をどのように学んでいるのか―複数言語環境で成長した留学生・大学生の日本語ライフストーリーをもとに
川上 郁雄, 尾関 史, 太田 裕子
早稲田教育評論 25-1 2012年 [査読有り]
川上, 郁雄, 尾関, 史, 太田, 裕子
早稲田教育評論 25 ( 1 ) 57 - 69 2011年03月
川上, 郁雄
早稲田日本語教育学 9 129 - 135 2011年02月 [査読有り]
川上, 郁雄
ジャーナル「移動する子どもたち」 - ことばの教育を創発する = Journal for Children Crossing Borders 1 1 - 21 2010年07月
川上 郁雄
早稲田日本語教育学 = Waseda studies in Japanese language education ( 8・9 ) 巻頭1 - 7 2010年
「移動する子ども」として成長した大学生の複数言語能力に関する語り-自らの言語能力をどう意識し,自己形成するのか
尾関 史, 川上 郁雄
複言語・複文化主義とは何か-ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文脈化へ 1 80 - 92 2010年 [査読有り]
川上, 郁雄, 中川, 智子, 河上, 加苗
早稲田日本語教育学 = Waseda studies in Japanese language education 4 1 - 14 2009年02月
川上 郁雄
リテラシーズ : ことば・文化・社会の日本語教育へ = Literacies : teaching Japanese for language, culture and society / リテラシーズ研究会 編 ( 4 ) 3 - 18 2009年
川上 郁雄
リテラシーズ : ことば・文化・社会の日本語教育へ = Literacies : teaching Japanese for language, culture and society / リテラシーズ研究会 編 ( 4 ) 182 - 188 2009年
「ベトナム難民」受け入れ三十年後のベトナム系住民の現在—特集 日本で暮らす外国人--地方都市の日系人・アジア人 ; 日本で暮らす外国人
川上 郁雄
アジア遊学 ( 117 ) 100 - 106 2008年12月
「移動する子どもたち」のプロフィシェンシーを考えるーJSLバンドスケールから見える「ことばの力」とは何か
川上郁雄
プロフィシェンシーを育てるー真の日本語能力をめざしてー 90 - 107 2008年12月 [招待有り]
The Vietnamese Diaspora in Japan and Their Dilemmas in the Context of Transnational Dynamism
Ikuo Kawakami
77 79 - 88 2008年03月
川上, 郁雄
早稲田大学日本語教育研究センター紀要 20 1 - 17 2007年07月
日本語能力の把握から実践への道すじ-「JSLバンドスケール」の意義と有効性-
川上 郁雄
「移動する子どもたち」と言語教育-ESLとJSLの教育実践から-国際研究集会プロシーディング 166 - 187 2007年
川上, 郁雄
早稲田大学日本語教育実践研究 = Journal of practical study on teaching Japanese language 5号 41 - 41 2006年12月
JSL児童の日本語能力の把握から実践への道すじ--新宿区立大久保小学校の実践をもとに—特集 年少者日本語教育の現在--その課題と展望
川上 郁雄, 髙橋 理恵
日本語教育 = Journal of Japanese language teaching / 日本語教育学会学会誌委員会 編 ( 128 ) 24 - 35 2006年01月
川上 郁雄
リテラシーズ : ことば・文化・社会の日本語教育へ = Literacies : teaching Japanese for language, culture and society / リテラシーズ研究会 編 ( 1 ) 3 - 18 2005年
A Longitudinal Survey and Study of Learning of Japanese by Foreign Settlers in Miyagi Prefecture
助川 泰彦, 市瀬 智紀, 川上 郁雄, 高橋 亜紀子
Bulletin of Tohoku University International Student Center Vol.8 53 - 58 2004年
助川 泰彦, 市瀬 智紀, 川上 郁雄
東北大学留学生センター紀要 / 東北大学留学生センター紀要編集委員会 編 ( 8 ) 53 - 58 2004年
「日本語を母語としない」児童生徒への地域における支援ネットワークに関する研究
川上 郁雄
早稲田大学日本語教育研究センター紀要 / 早稲田大学日本語教育研究センター 編 ( 18 ) 1 - 12 2004年
書評 関口知子著『在日日系ブラジル人の子どもたち--異文化間に育つ子どものアイデンティティ形成』(明石書店 2003年)
川上 郁雄
異文化間教育 = Intercultural education / 異文化間教育学会紀要編集委員会 編 ( 19 ) 114 - 117 2004年
川上, 郁雄
早稲田大学日本語研究教育センター紀要 16 17 - 35 2003年04月
川上, 郁雄
早稲田大学日本語教育研究 2号 1 - 16 2003年03月
定住と越境--日本とオーストラリアのベトナム系住民を例に—特集 越境の中の近現代日本
川上 郁雄
大阪大学日本学報 / 大阪大学大学院文学研究科日本学研究室『日本学報』編集委員会 編 ( 22 ) 7 - 22 2003年03月
Kawakami Ikuo
International journal of Japanese sociology : IJJS 12 48 - 67 2003年
助川 泰彦, 市瀬 智紀, 川上 郁雄
東北大学留学生センター紀要 / 東北大学留学生センター紀要編集委員会 編 ( 6 ) 31 - 36 2002年
川上 郁雄
ベトナムの社会と文化 = Society and culture of Vietnam = Xã hội và văn hóa Việt Nam / ベトナム社会文化研究会 編 ( 1 ) 134 - 155 1999年06月
ニュージーランドの中等教育における日本語教育--教員研修でのアンケート調査を踏まえて
川上 郁雄, 宇田川 洋子
宮城教育大学紀要. 第1分冊, 人文科学・社会科学 ( 31 ) 1 - 14 1996年
オーストラリアの初等・中等教育における日本語教育 : クィーンズランド州における経験から
川上 郁雄, 藤長 かおる
世界の日本語教育. 日本語教育事情報告編 2 195 - 211 1995年01月
Adaptation and Life Strategies of Vietnamese Refugees in Japan
Kawakami Ikuo
Bulletin of Miyagi University of Education. Pt. 1, The humanities and social sciences 30 1 - 15 1995年
Classroom Activities for Communication in Japanese--At the secondary school level in Australia
川上 郁雄, 正野 葉子
宮城教育大学紀要. 第1分冊, 人文科学・社会科学 ( 29 ) p1 - 13 1994年
川上 郁雄
日本語教育 = Journal of Japanese language teaching / 日本語教育学会学会誌委員会 編 ( 73 ) p154 - 166 1991年03月
人文学を社会に開くには。その理論と実践を学ぶ
川上郁雄( 担当: 分担執筆, 担当範囲: 8章 公共日本語教育学の理論と実践)
文学通信 2025年03月 ISBN: 9784867660867
ベトナム系ディアスポラ・ハンドブック
川上郁雄( 担当: 分担執筆, 担当範囲: 日本のベトナム系ディアスポラ)
2024年 ISBN: 9780367463960
移動とことば2
川上郁雄, 三宅和子, 岩﨑典子( 担当: 共編者(共編著者), 担当範囲: 序章;第9章)
くろしお出版 2022年03月 ISBN: 9784874248966
「移動する子ども」学
川上, 郁雄
くろしお出版 2021年03月 ISBN: 9784874248553
日本語を学ぶ子どもたちを育む「鈴鹿モデル」 : 多文化共生をめざす鈴鹿市+早稲田大学協働プロジェクト
川上, 郁雄
明石書店 2021年03月 ISBN: 9784750351834
探究型アプローチの大学教育実践 : 早大生が「複言語で育つ子ども」を考える授業
川上, 郁雄, 12名の早稲田大学学部生
くろしお出版 2020年11月 ISBN: 9784874248447
JSLバンドスケール : 子どもの日本語の発達段階を把握し、ことばの実践を考えるために
川上, 郁雄
明石書店 2020年08月 ISBN: 9784750350776
JSLバンドスケール : 子どもの日本語の発達段階を把握し、ことばの実践を考えるために
川上, 郁雄
明石書店 2020年08月 ISBN: 9784750350783
移動とことば
川上, 郁雄, 三宅, 和子, 岩崎, 典子( 担当: 共編者(共編著者))
くろしお出版 2018年08月 ISBN: 9784874247747
文化を映す鏡を磨く : 異人・妖怪・フィールドワーク
橘, 弘文, 手塚, 恵子, 川上, 郁雄, 村上, 和弘, 魯, 成煥, Hayek, Matthias, 香川, 雅信, 今井, 秀和, 飯倉, 義之, 徳永, 誓子, 木場, 貴俊, 村山, 弘太郎, 松村, 薫子, 真鍋, 昌賢, 川村, 清志, 安井, 眞奈美, 山, 泰幸
せりか書房 2018年07月 ISBN: 9784796703758
公共日本語教育学 : 社会をつくる日本語教育
川上, 郁雄( 担当: 編集)
くろしお出版 2017年06月 ISBN: 9784874247334
マルチ・エスニック・ジャパニーズ : ○○系日本人の変革力
佐々木, てる, 南川, 文里, 佐藤, 成基, 石井, 由香, 川上, 郁雄, 小林, 真生, 李, 洙任, 陳, 天璽, 倉石, 一郎, 高畑, 幸, 梶村, 美紀, 倉田, 有佳, 南, 誠, 中山, 大将
明石書店 2016年05月 ISBN: 9784750343587
日本に住む多文化の子どもと教育 : ことばと文化のはざまで生きる
Miyazaki, Sachie, 坂本, 光代, Caltabiano, Yuriko Miyamoto, Morales, Leiko Matsubara, 川上, 郁雄, 杉村, 美紀, 山西, 優二, 杉村, 美佳, 松田, デレク
Sophia University Press 上智大学出版,ぎょうせい (発売) 2016年04月 ISBN: 9784324101414
日本語を学ぶ/複言語で育つ : 子どものことばを考えるワークブック
川上, 郁雄, 尾関, 史, 太田, 裕子 (日本語教育)
くろしお出版 2014年10月 ISBN: 9784874246351
「移動する子ども」という記憶と力 : ことばとアイデンティティ
川上, 郁雄( 担当: 編集)
くろしお出版 2013年03月 ISBN: 9784874245798
移民の子どもたちの言語教育 : オーストラリアの英語学校で学ぶ子どもたち
川上, 郁雄
オセアニア出版社 2012年03月 ISBN: 9784872031072
「移動する子どもたち」のことばの教育学
川上, 郁雄
くろしお出版 2011年02月 ISBN: 9784874245118
私も「移動する子ども」だった : 異なる言語の間で育った子どもたちのライフストーリー
川上, 郁雄
くろしお出版 2010年05月 ISBN: 9784874244746
海の向こうの「移動する子どもたち」と日本語教育 : 動態性の年少者日本語教育学
川上, 郁雄( 担当: 編集)
明石書店 2009年09月 ISBN: 9784750330617
「移動する子どもたち」のことばの教育を創造する : ESL教育とJSL教育の共振
川上, 郁雄, 石井, 恵理子, 池上, 摩希子, 斎藤, ひろみ, 野山, 広
ココ出版 2009年03月 ISBN: 9784904595015
「移動する子どもたち」の考える力とリテラシー : 主体性の年少者日本語教育学
川上, 郁雄( 担当: 編集)
明石書店 2009年01月 ISBN: 9784750329161
変貌する言語教育 : 多言語・多文化社会のリテラシーズとは何か
佐々木, 倫子, 細川, 英雄, 砂川, 裕一, 川上, 郁雄, 門倉, 正美, 牲川, 波都季
くろしお出版 2007年10月 ISBN: 9784874243954
Japan's globalization
川上, 郁雄, Mock, John
Kumpul 2007年 ISBN: 9784875510598
「移動する子どもたち」と日本語教育 : 日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考える
川上, 郁雄, 薮本, 容子, 森沢, 小百合, 武蔵, 祐子, 朴, 智映, 太田, 裕子 (日本語教育), 齋藤, 恵 (日本語講師), 間橋, 理加, 小池, 愛, 渡辺, 啓太 (学校教諭), 渡辺, 千奈津( 担当: 編集)
明石書店 2006年10月 ISBN: 4750324175
新時代の日本語教育をめざして : 早稲田から世界へ発信
宮崎, 里司, 川上, 郁雄, 細川, 英雄
明治書院 2006年03月 ISBN: 4625703085
越境する家族 : 在日ベトナム系住民の生活世界
川上, 郁雄
明石書店 2005年09月 ISBN: 475039016X
異文化理解と情報
川上, 郁雄, 鳥谷, 善史, 佐治, 圭三, 真田, 信治
東京法令出版,凡人社 (発売) 2004年06月 ISBN: 4809062414
日本語指導の必要な児童生徒に関する教育方法と教材開発の研究
川上, 郁雄
[川上郁雄] 2004年03月
国際化する日本社会
梶田, 孝道, 宮島, 喬, 丹野, 清人, 上林, 千恵子, 町村, 敬志, 西澤, 晃彦, 池上, 重弘, 川上, 郁雄, 樋口, 直人
東京大学出版会 2002年03月 ISBN: 4130341510
在日ベトナム人の家族とその多国間ネットワークに関する文化人類学的研究
川上, 郁雄
[宮城教育大学] 2001年03月
越境する家族 : 在日ベトナム系住民の生活世界
川上, 郁雄
明石書店 2001年02月 ISBN: 4750313858
Designing the future of Japanese language teaching in Australia : new perspective between Australia and Japan
川上, 郁雄, 宮崎, 里司
Japan Foundation Sydney Language Centre 2001年
Ip, David, 川上, 郁雄, Duivenvoorden, Karel, Tye, Lee Chang
Multicultural Centre, University of Sydney 1994年 ISBN: 0867589396
A report on the local integration of Indo-Chinese refugees and displaced persons in Japan
川上, 郁雄
UNHCR, the UN Refugee Agency
宮城県の多言語多文化化に関する調査
その他
豪州・ブリスベン市におけるベトナム人の宗教生活に関する研究
オーストラリアの産業界に求められる人材育成と日本語教育に関する研究
在日ベトナム人の家族とその多国間ネットワークに関する文化人類学的研究
在日ベトナム人社会に見られる異文化適応と文化変容に関する研究
神戸市のベトナム系コミュニティに関する研究
オーストラリア・ブリスベン市在住のベトナム人の定住実態調査
関東・関西在住ベトナム人の定住実態調査
オーストラリア・ニュージーランドの初等・中等教育における日本語教育に関する研究
年少者の日本語教育実践に関わる指導者の実践力を向上させるための持続可能な方法とはー「JSLバンドスケール」を使用したオンライン講座の実践を通して
川上郁雄, 塩田紀子
2023年度日本語教育学会秋季大会
発表年月: 2023年11月
「移動する子ども」学からケイショウゴ教育を考える
川上郁雄, 太田裕子, 中野千野, 大山美佳
豪州日本研究学会研究大会/国際繋生語大会
発表年月: 2023年09月
「移動する子ども」学から、「継承語教育」を考える
川上郁雄 [招待有り]
韓国日本語学会 第46回 国際学術発表大会
発表年月: 2022年09月
未来へ繋ぐ日本語教育ーことばと移動、変わり続けるグローバル社会で目指すこと
川上郁雄 [招待有り]
カナダ日本語教育振興会2022年研究大会
発表年月: 2022年08月
年少者日本語教育に関わる実践者の実践力向上を目指す持続可能な方法の開発
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
川上 郁雄
海外で日本語を学ぶ子どもの日本語能力の把握と教材研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
川上 郁雄
年少者日本語教育の協働的実践研究-教科学習を通して身に付く「ことばの力」の検証-
研究期間:
日本は移民国家か?日本とオーストラリアにおける移住者の市民意識と帰属感の比較研究
研究期間:
日本国外の日本語バイリンガル若年層の複数言語能力意識の把握と日本語教育方法の開発
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
川上 郁雄, 尾関 史, 太田 裕子, 太田 裕子
国連の平和活動とビジネス : 紛争、人の移動とガバナンスを軸として
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
佐藤 安信, 星野 俊也, 山下 晋司, 石田 勇治, 中西 徹, 遠藤 貢, 山影 進, 庄司 真理子, 川上 郁雄, 小泉 康一, 中山 幹康, 新垣 修, 槍目 雅
年少者日本語教育の実践的研究-JSLカリキュラムの検証とプログラム開発-
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
池上 摩希子, 川上 郁雄, 齋藤 ひろみ, 石井 恵理子, 野山 広
新しい日本人のアイデンティティ:市民権と多文化共生をめぐる移民者の物語
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
川上 郁雄, CHAPMAN D.R.
年少者日本語教育における日本語教材、教授法および教育行政システム構築に関する研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
川上 郁雄, 市瀬 智紀
日本語教育と文化リテラシーに関する理論的研究、および、実践モデルの開発
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
佐々木 倫子, 細川 英雄, 門倉 正美, 川上 郁雄, 砂川 裕一, 牲川 波都季
地域における定住外国人の主体的な日本語習得に関する縦断的調査・研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
市瀬 智紀, 川上 郁雄, 助川 泰彦, 高橋 亜紀子
ベトナムに関する日本人類学研究の総括と現地への発信
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
末成 道男, 中西 裕二, 宮澤 千尋, 樫永 真佐夫, 李 鎮栄, 芹澤 知広, 川上 郁雄
在日ベトナム人の家族とその多国間ネットワークに関する文化人類学的研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
川上 郁雄
大学におけるカリキュラム改革-教育大学とリベラルアーツカレッジにおける比較
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
武元 英夫, BRESSOUD Dav, 竹内 洋, 瓜生 等, 降矢 美彌子, 安江 正治, 前田 順一, 渡辺 徹, 花島 政三郎, LAINE James, KURTHーSCHAI ルサン, LANEGRAN Dav, PARSON Kathl, WEATHERFORD ジャック, SUTHERLAND A, 石黒 広昭, 川上 郁雄, 本間 明信, 猪平 真理, 森田 稔
在日ベトナム人社会に見られる異文化適応と文化変容に関する研究
日本語教育の必要な児童生徒に関する教育方法と教材開発の研究
日本国外にいる日本語バイリンガル若年層の複数言語能力、言語観に関する質的調査
「公共日本語教育学」構築の意味 : 実践の学の視点から (日研設立15周年特集 新たな日本語教育学の構築をめざして : 日研の挑戦)
川上 郁雄
早稲田日本語教育学 = Waseda studies in Japanese language education ( 20 ) 33 - 47 2016年06月
SENDプログラムを通して求められる能力とは : 日本語教育とグローバル化 (特集 大学の世界展開力とSENDプログラム)
宮崎 里司, 川上 郁雄
早稲田日本語教育学 = Waseda studies in Japanese language education ( 17 ) 1 - 8 2015年05月
複言語で育つ大学生のことばとアイデンティティを考える授業実践
川上 郁雄
早稲田日本語教育実践研究 = Waseda practical studies in Japanese language education ( 3 ) 33 - 42 2015年
「移動する子どもたち」は大学で日本語をどのように学んでいるのか--複数言語環境で成長した留学生・大学生の日本語ライフストーリーをもとに
川上 郁雄, 尾関 史, 太田 裕子
早稲田教育評論 25 ( 1 ) 57 - 69 2011年
オーストラリアにおけるESL教育および日本語教育に関する研究
オーストラリア モナシュ大学
オーストラリア ニューサウスウェールズ大学
複数言語環境で成長する子どもの日本語能力と教材開発に関する日本語教育方法の構築
2013年 尾関 史, 太田 裕子
Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API in February 15, 2026, via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .