経歴
-
2022年04月-継続中
早稲田大学名誉教授
-
1997年04月-2022年03月
早稲田大学教授
-
1991年04月-1997年03月
成蹊大学 助教授/教授
-
1974年07月-1991年03月
特殊法人アジア経済研究所 研究員/研究主任
2026/01/17 更新
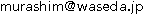
早稲田大学名誉教授
早稲田大学教授
成蹊大学 助教授/教授
特殊法人アジア経済研究所 研究員/研究主任
東京大学 法学部 第3類(政治学)
東南アジア大陸部、タイ近現代史、近代日タイ関係史、仏教ナショナリズム、仏教交流、テーラワーダ仏教近代史、華僑華人、在タイ日本人社会
村嶋英治著『南北仏教の出会い:近代タイにおける日本仏教者,1888-1945』への補遺・修正:吉丸徹太郎、重田友介を中心に
村嶋英治
『アジア太平洋討究』 ( 49 ) 51 - 97 2024年10月
近代タイにおける大乗仏教と「小乗仏教」:タイ国王の国内大乗仏教徒処遇及び日本の大乗仏教がタイ仏教呼称に及ぼした意図せざる影響
村嶋英治
『アジア太平洋討究』 ( 47 ) 49 - 72 2023年12月
Comments on Katherine Bowie's Study of Khruba Srivichai
Eiji Murashima
Journal of the Siam Society 111 ( 2 ) 23 - 28 2023年06月 [査読有り] [招待有り] [国際誌]
タイにおける組織的日本文化広報の先駆者:日泰文化研究所主事平等通昭(通照)の「興亜興仏」的文化交流事業(1940ー43年)
村嶋英治
『アジア太平洋討究』 ( 46 ) 1 - 54 2023年03月
クルーバー・シーウィチャイの第2回バンコク軟禁(1935年11月ー36年5月)の背景、過程及び結末:中央サンガ・エリートによるシーウィチャイ派弾圧処分の徹底
村嶋英治
『アジア太平洋討究』 ( 45 ) 1 - 43 2022年12月
ต้นกำเนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย
เออิจิ มูราชิมา
The Thammasat Journal of History = วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ 6 ( 2 ) 19 - 79 2019年07月 [招待有り]
戦後の日本人納骨堂と辻政信大佐
村嶋英治
『泰国日本人納骨堂建立八十周年記念誌』 67 - 75 2017年11月
堀井龍司憲兵中佐手記, タイ国駐屯憲兵隊勤務 (1942-45年) の想い出 : 付録 18方面軍参謀 原寿雄少佐手記
村嶋 英治
早稲田大学アジア太平洋研究センター研究資料シリーズ ( 7 ) 1 - 187 2017年03月
Thailand and Indochina 1945-1950
村嶋英治
Journal of Asia-Pacific Studies (Waseda University) ( 25 ) 137 - 176 2015年12月
戦前期タイ国の日本人会および日本人社会:いくつかの謎の解明
村嶋英治
『タイと共に歩んで、泰国日本人会百年史』 13 - 46 2013年09月
The Origins of Chinese Nationalism in Thailand
Eiji Murashima
Journal of Asia-Pacific Studies ( 21 ) 149 - 172 2013年08月
นวน เจียวัยหนุ่ม กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(in Thai)
เออิจิ มูราชิมาเขียน ปราการ กลิ่นฟุ้งแปล
ฟ้าเดียวกัน 9 ( 1 ) 187 - 221 2011年01月
タイ華僑社会における中国ナショナリズムの起源
村嶋英治
『岩波講座;東アジア近現代通史;第二巻;日露戦争』 222 - 243 2010年10月
Eiji Murashima
Journal of Asia-Pacific Studies(Waseda University) ( 12 ) 1 - 42 2009年03月
タイにおける共産主義運動と中国革命―タイ共産党の成立をめぐって
村嶋英治
『岩波講座東南アジア史第8巻』岩波書店 259 - 282 2002年02月
タイ国の立憲革命期における文化とナショナリズム
村嶋英治
『岩波講座東南アジア史第7巻』岩波書店、 241 - 270 2002年01月
The Thai-Japanese Alliance and the Chinese of Thailand”
Eiji Murashima
Paul H. Kratoska ed. Southeast Asian Minorities in the Wartime Japanese, Routledge Cruzon. 199 - 222 2002年 [査読有り]
日タイ関係 1945-1952年: 在タイ日本人及び在タイ日本資産の戦後処理を中心に
村嶋英治
『アジア太平洋討究』(早稲田大学アジア太平洋研究センター) ( 1 ) 141 - 162 2000年01月
สัมพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่นกับชาวจีนในประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
Eiji Murashima(translated by Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ฮายะโอะ ฟูกุย ed,ญี่ปุ่น-ไทย-อุษาคเนย์(Japanese scholarships on Thailand and Southeast Asia) 111 - 200 1998年
1940年代におけるタイの植民地体制脱却化とインドシナの独立運動
村嶋英治
礒辺啓三編『ベトナムとタイ、経済発展と地域協力』大明堂 110 - 218 1998年
タイ華僑の政治活動 ― 5・30運動から日中戦争まで
村嶋英治
原不二夫編『東南アジア華僑と中国』 アジア経済出版会 263 - 364 1993年08月
タイにおける政治体制の周期的転換
村嶋英治
萩原宜之・村嶋英治編『ASEAN諸国の政治体制』アジア経済研究所 135 - 190 1987年03月
現代タイにおける公的国家イデオロギーの形成 -民族的政治共同体 (チャート) と仏教的王制-:アジアの民族と国家 東南アジアを中心として
村嶋 英治
『国際政治』(日本国際政治学会) ( 84 ) 118 - 135 1987年 [査読有り]
第2次大戦期に関する日本側・タイ側の資料と研究成果
村嶋英治
Essays on Vietnam and Thailand during the Second World War Edited by Masaya Shiraishi and Bruce M. Lockhart,pp.12-24. 2018年03月
中国に帰ったタイ華僑共産党員-欧陽恵氏のバンコク、延安、大連、吉林、北京での経験-(早稲田大学リポジトリにてDownload可)
村嶋 英治, 鄭 成
早稲田大学アジア太平洋研究センター リサーチ・シリーズ ( 1 ) 1 - 241 2012年12月
36年目のタイ地域研究
村嶋英治
『アジア学のすすめ 第1巻: アジア政治・経済論』 86 - 107 2010年06月
2010年3月-5月赤シャツ派(UDD)のバンコク市街占拠闘争--準備された政変・革命の挫折 (特集 バンコクの騒乱を考える)
村嶋 英治
『タイ国情報』 44 ( 3 ) 1 - 44 2010年05月
カンボジア共産党ナンバー・ツー,ヌオン・チア(Nuon Chea)のバンコク時代(1942年-1950年)(早稲田大学リポジトリにてDownload可)
村嶋 英治
『アジア太平洋討究』 ( 11 ) 85 - 121 2008年10月
การปฎิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม: มิถุนายน ๒๔๗๕
ยาสุกิจ ยาตาเบ, 矢田部保吉著เขียน, เออิจิ มูราชิม村嶋英治และ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ナカリン, メークトライラット 共訳
ศิลปวัฒนธรรม Art & Culture Magazine 26 ( 8 ) 80 - 98 2005年06月
第二次世界大戦期間的日泰同盟及泰国華僑(中国語)
村嶋英治
早稲田大学21世紀COE「現代アジア学の創生」ワーキングペーパー No.12,25p.(中国語) 2005年01月
矢田部公使のタイ研究及び留学生事業ー今日への遺産
村嶋英治
『特命全権公使矢田部保吉』 115 - 131 2002年
การเปรียบเทียบข้อมูลไทย-ญี่ปุ่น :กรณีการส่งทหารเข้ารัฐฉาน(สหรัฐไทยใหญ่) ในพ.ศ.๒๔๘๕
เออิจิ มูราชิมา
จุลสารไทยคดีศึกษา 17 ( 3 ) 32 - 46 2001年02月
Kan priapthiap khomun Thai-Jipun:karani kan song thahan Thai khao Rat Shan nai pho.so.2485
Eiji Murashima
Thaikhadi Suksa (in Thai) Vol.17 ( 3 ) 32 - 46 2001年02月
タイの歴史記述における記念顕彰本的性格
村嶋英治
『上智アジア学』 ( 17 ) 33 - 57 2000年03月
タイ近代国家の形成
村嶋英治
石井米雄、桜井由躬雄編『東南アジア史 Ⅰ』(新版世界各国史第5巻、山川出版社)第Ⅱ部第8章 397 - 439 1999年12月
Kan priapthiap khomun Thai-Jipun:karani kan song thahan Thai khao Rat Shan nai pho.so.2485
Eiji Murashima
Thammasat University Journal (in Thai) Vol.25 ( 2 ) 87 - 99 1999年05月
5章 タイにおける国民国家 ー 歴史と展望ー
村嶋英治
西川長夫・山口幸二・渡辺公三編『アジアの多文化社会と国民国家』人文書院 102 - 129 1998年10月
タイにおける国民国家、歴史と展望
村嶋英治
『言語文化研究』(立命館大学国際言語文化研究所) 9 ( 3 ) 211 - 228 1998年01月
タイの官僚制―競争試験制度を中心として
村嶋英治
岩崎育夫、萩原宜之編『ASEAN諸国の官僚制』アジア経済研究所刊 163 - 191 1996年03月
タイにおける政党政治の成立
村嶋英治
村嶋英治、萩原宜之、岩崎育夫編『ASEAN諸国の政党政治』アジア経済出版会 149 - 182 1993年01月
「タイの民主化」、「タイ国民にとっての王室」、「タイの暫定首相」
村嶋英治
『アエラ』3件 1992年5月26日、6月2日、6月23日号 1992年05月
軍部支配と政治統合:タイ1932年革命期における
村嶋英治
矢野暢編・講座東南アジア学第七巻,『東南アジアの政治』 弘文堂 81 - 101 1992年03月
Democracy and the Development of Political Parties in Thailand, 1932-1945
Eiji Murashima
Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat, Somkiat Wanthana, The Making of Modern Thai Political Parties,アジア経済研究所JRP Series No.86 1991,pp.1-54. 1 - 54 1991年
อุดมการณ์แห่งรัฐไทยสมัยใหม่(in Thai)
Eiji Murashima著, เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช訳
รวมบทความประวัติศาสตร์タイ歴史学会編『歴史学論文集』(in Thai) ( 13 ) 84 - 105 1991年
เบื้องหลังการเข้าไปอย่างสันติของกองทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย : ในช่วงต้นของประกาศสงคราม(ธันวาคม ๒๔๘๔)
Kushida Masao, มูราชิมา เออิจิ
ไทย-ญี่ปุ่นศึกษา = Thai Japanese Studies 1989 ( 4 ) 74 - 81 1989年04月
Buanglang kankhaopai yang santhi khong kongthahan jipun nai prathet Thai nai chuangton khong kanprakat songkhram(櫛田正夫「大東亜戦争開始当初に於ける日本軍の泰国平和進駐事情」のタイ語訳)
Eiji Murashima
Thai-Jipun Suksa(Thai Japanese Studies,Thammasat University)(in Thai) April 1989 74 - 81 1989年04月
タイにおける中国人のタイ人化
村嶋英治
岡部達味編『ASEANにおける国民統合と地域統合』日本国際問題研究所 115 - 141 1989年03月 [査読有り]
แผนการบุกของญี่ปุ่นกับบทบาทนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม
Yahara Hiromichi, เออิจิ มูราชิมา
ศิลปวัฒนธรรม = Art & Culture 7 ( 9 ) 82 - 91 1986年07月
Phaenkan buk khong Jipun kap botbat nayok ratthamontori Chomphon P.Phibulsongkhram (八原博通「泰国進駐とピブン首相」のタイ語訳)
Eiji Murashima
Sinlapa Watthanatham(Art&Culture)(in Thai) Vol.7 ( no.9 ) 82 - 91 1986年07月
Building of the Modern Thai Official State Ideology in the Reign of King Chulalongkorn and King Vajiravudh
Eiji Murashima
Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat, Political Thoughts of the Thai Military in Historical Perspective,JRP Series55, Institute of Developing Economies 1 - 43 1986年03月
タイー必要な国民の政治参加の制度化
村嶋英治
総合研究開発機構(NIRA)10周年記念研究『アジア・太平洋地域の将来展望に関する研究』NRO-84-6 279 - 301 1985年10月
最近のタイの政情
村嶋英治
『アジア時報』 1975年5月号,pp.60-67. 1975年05月
村嶋英治( 担当: 単著)
早稲田大学アジア太平洋研究センター 2023年09月 ISBN: 9784910603254
堀井龍司憲兵中佐手記、タイ国駐屯憲兵隊勤務(1942ー45年)の想い出 付録 18方面軍参謀 原寿雄少佐手記
村嶋英治
早稲田大学アジア太平洋研究センター研究資料シリーズ No.7 2017年03月
中国に帰ったタイ華僑共産党員:欧陽恵氏のバンコク、延安、大連、吉林、北京での経験(早稲田大学リポジトリにてDownload可)、241頁
村嶋英治, 鄭成
早稲田大学アジア太平洋研究センター、リサーチ・シリーズ第1号 2012年12月
Kamnoet Phak Communist Sayam 1927-1936(暹羅共産党の誕生)in Thai(タイ語) (早稲田大学リポジトリにてDownload可)
Eiji Murashima著, Kosit Tiptiempong訳
Matichon 2012年 ISBN: 9789740209904
礒辺啓三編『ベトナムとタイ、経済発展と地域協力』大明堂
村嶋英治, 年代におけるタイの植民地体制脱却化とインドシナの独立運動
大明堂 1998年12月 ISBN: 4470500593
Hayao Fukui,Charnvit Kasetsiri eds,Jipun-Thai-Utsakhane(Japanese Scholarships on Thailand and Southeast Asia), Eiji Murashima สัมพันธมิตรไทย-ญี่ปุ่นกับชาวจีนในประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
村嶋英治
Munnithi Khrongkan Tamra,Bangkok (in Thai) 1998年01月 ISBN: 9748960897
Eiji Murashima 著, Eiji Murashima, Worasak Mahatthanobon共訳
Institute of Asian Studies,Chulalongkorn University,237p.( in Thai) 1996年 ISBN: 9746329618
村嶋英治・萩原宜之・岩崎育夫編『ASEAN諸国の政党政治』
村嶋英治
アジア経済研究所 1993年01月 ISBN: 4258044261
The Making of Modern Thai Political Parties
Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat, Somkiat Wanthana
JRP Series No.86,Institute of Developing Economies,Tokyo. 1991年
萩原宜之・村嶋英治編『ASEAN諸国の政治体制』
村嶋英治, タイにおける政治体制の周期的転換, 執筆
アジア経済研究所 1987年03月 ISBN: 4258043575
Vietnam-Indochina-Japan relations during the Second World War : documents and interpretations
白石, 昌也, Nguyễn, Văn Khánh, Lockhart, Bruce McFarland( 担当: 分担執筆, 担当範囲: pp.155-195 Eiji Murashima,Thailand and Indochina 1945-1951)
Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS) 2017年02月 ISBN: 9784902590715
『アジア・太平洋戦争辞典』、吉川弘文館
村嶋英治ディレーク・チャイヤナームDirek Jayanama(p.435) プレーク・ピブーンソンクラームPlaek Phibunsongkhram, (p.592) プリーディー・パノムヨンPridi Phanomyong (pp.590-591) ワンワイタヤーコンPrince Wanwaithayakon Worawan親王(pp.717-718)
2015年11月
『Kanpathiwat lae Kanplianplaeng nai Prathet Sayam』(矢田部保吉著『シャム国革命政変の回顧』タイ語訳第2版)
Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat訳
Matichon 2014年06月 ISBN: 9789743239779
『タイと共に歩んで、泰国日本人会百年史』,pp.10-46所収、「戦前期タイ国の日本人会および日本人社会:いくつかの謎の解明」
村嶋英治
泰国日本人会 2013年09月
戦前の財団法人日本タイ協会会報集成解題(早稲田大学リポジトリにてDownload可)
村嶋英治, 吉田千之輔編著
早稲田大学アジア太平洋研究センター、研究資料シリーズ第4号 2013年02月
Pasuk Phongpaichit;Baker, Christopher John eds,Essays on Thailand's economy and society : for Professor Chatthip Nartsupha at 72
Eiji Murashima( 担当: 共著, 担当範囲: pp.127-155 The Origins of Chinese Nationalism in Thailand)
Sangsan 2013年01月 ISBN: 9789749936252
『Phu Banchakan Chaophut:khwam songcham khong naiphon Nakamura kiaokap muangthai samai songkhram maha echia burapha』(中村明人著『ほとけの司令官ー駐タイ回想録』のタイ語訳第3版)
Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat訳
Matichon 2012年06月
『岩波講座 東アジア近現代通史、第二巻(日露戦争と韓国併合)』pp.222-243.
村嶋英治, タイ華僑社会における中国ナショナリズムの起源( 担当: 共著)
岩波書店 2010年10月
『アジア学のすすめ、第1巻、アジア政治・経済論』
早稲田大学アジア研究機構叢書
弘文堂 2010年06月 ISBN: 9784335501111
『現代タイ動向 2006−2008』
日本タイ協会編
めこん 2008年12月 ISBN: 9784839602192
歴史学研究会編『世界史史料、第9巻』
村嶋英治, シャムのチャクリー改革
岩波書店 2008年06月
kanpathiwat lae kanplianplaeng nai prathet sayam(矢田部保吉『シャム国革命政変の回顧』tタイ語全訳)
Eiji Murashima, Nakharin Mektraira, 和文タイ語訳(in, Tha
Matichon 2007年06月
歴史学研究会編『世界史史料、第10巻』
村嶋英治, タイ立憲革命, 泰緬鉄道, の項執筆
岩波書店 2006年12月 ISBN: 4000263889
kanpathiwat lae kanplianplaeng nai prathet sayam(矢田部保吉『シャム国革命政変の回顧』タイ語全訳)
Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat
Faculty of Political Science,Thmasat University seminar(Dec.2004) paper 56p. 2004年12月
黒田日出男他編『日本史文献事典』
村嶋英治, ピブーン, 岩波書店, 年, の項執筆
弘文堂 2003年12月 ISBN: 4335250584
Phu Banchakan Chaophut:khwam songcham khong naiphon Nakamura kiaokap muangthai samai songkhram maha echia burapha中村明人『ほとけの司令官ー駐タイ回想録』の1991年タイ語訳版の第二版
Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat和文タイ語訳
Matichon (in Thai) 2003年11月 ISBN: 9743230602
綾部恒夫・林行夫編『タイを知るための60章』
村嶋英治は, 植民地にならなかったタイ, 絶対王制と立憲君主制, チュラーロンコーン」「ピブーン, ソンクラーム」執筆
明石書店 2003年05月 ISBN: 475031725X
『岩波講座、東南アジア史、別巻』
村嶋英治, タイ語史料, 項執筆
岩波書店 2003年01月 ISBN: 4000110705
矢田部会編『特命全権公使 矢田部保吉』
村嶋英治, 矢田部公使のタイ研究及び留学生事業, 今日への遺産, 章執筆
個人書店 2002年12月 ISBN: 4860910443
『岩波講座東南アジア史、第8巻』
村嶋英治, タイにおける共産主義運動と中国革命, 章執筆
岩波書店 2002年02月 ISBN: 4000110683
Paul H. Kratoska ed.,Southeast Asian Minorities in the Wartime Japanese Empire,
Eiji Murashima"The Thai-Japanese Alliance, the Chinese of Thailand
Routledge Curzon 2002年 ISBN: 070071488X
『岩波講座東南アジア史、第7巻』
村嶋英治, タイ国の立憲革命期における文化とナショナリズム, 章執筆
岩波書店 2002年01月 ISBN: 4000110675
石井米雄・桜井由躬雄編『東南アジア史 Ⅰ』
村嶋英治, タイ近代国家の形成, 章執筆
山川出版社 1999年12月 ISBN: 4634413507
『歴史学事典、第7巻、戦争と外交』および『歴史学事典、第12巻、王と国家』
村嶋英治は各, 大タイ主義」, チュラーロンコーン王, の項執筆
弘文堂 1999年 ISBN: 433521037X
西川長夫他編『アジアの多文化社会と国民国家』
村嶋英治, タイにおける国民国家, 歴史と展望, 章執筆
人文書院 1998年09月 ISBN: 4409230301
『ASEAN諸国の官僚制』
村嶋英治, 章執筆
アジア経済研究所, 1996年03月 ISBN: 4258044601
『世界民族問題事典』
村嶋英治, チャート, の項執筆
平凡社 1995年 ISBN: 4582132014
安中章夫編『東南アジア:政治・社会』(地域研究シリーズ6)
221-242頁 村嶋英治, タイ国における地方選挙と地方リーダー, ナコンサワン県のケーススタディ( 担当: 共著)
アジア経済研究所,アジア経済出版会 (発売) 1993年08月 ISBN: 425822006X
原不二夫編『東南アジア華僑と中国』
村嶋英治, タイ華僑の政治活, 運動から日中戦争まで
アジア経済研究所 1993年08月 ISBN: 4258044369
『タイの事典』
村嶋英治, 対外関係, 民族主義, 項目執筆
同朋社 1993年 ISBN: 4810408531
上智大学アジア文化研究所編『入門 東南アジア研究』
村嶋英治, 章, 国家と政治, 章執筆
めこん 1992年05月 ISBN: 483960066X
矢野暢編『東南アジアの政治』(講座東南アジア学第7巻)
村嶋英治, 軍部支配と政治統合
弘文堂、 1992年03月 ISBN: 4335000278
Phu Banchakan Chaophut(中村明人著『ほとけの司令官ー駐タイ回想録』のタイ語訳)
Eiji Murashima, Nakharin Mektraira, 和文タイ語訳
Munnithi Khrongkan Tamra,Bangkok,209p. 1991年12月
『戦後史大事典』
村嶋英治, 戦後史文献解題ータイ, の項執筆
三省堂 1991年 ISBN: 4385154325
岡部達味編『ASEANにおける国民統合と地域統合』
村嶋英治, タイにおける中国人のタイ人化, の章執筆
国際問題研究所 1989年03月 ISBN: 4819301063
『東南アジアを知る事典』
村嶋英治, タイの文化, タイの政治, の項執筆
平凡社 1986年 ISBN: 4582126049
Political Thoughts of the Thai Military in Historical Perspective
Eiji Murashima, Nakharin Mektrairat
JRP Series No.55,Institute of Developing Economies,Tokyo 1986年
『タイ国労働保護法解説』
村嶋英治タイ文和訳
バンコク日本人商工会議所、232p. 1985年11月
『アジア・太平洋地域の将来展望に関する研究』(NIRA10周年記念研究)
村嶋英治, 章執筆
総合研究開発機構編 1985年10月 ISBN: 4795544697
『平凡社大百科大事典』第8巻
村嶋英治, タイの政治, の項執筆
平凡社 1985年
タイ国主要穀菽類の収穫後処理実態調査
村嶋英治, 上田克巳タイ文和訳
国際協力事業団,農開技JR 83-45,157頁 1983年06月
『タイ国労働法及び関係内務省令』
村嶋英治タイ文和訳
バンコク日本人商工会議所、119p. 1982年
山崎利男・安田信之編『アジア諸国の法制度』
村嶋英治, タイの法制度, 章執筆
アジア経済研究所 1980年03月 ISBN: 4258090972
アジア経済研究所編『発展途上国の自動車産業』
村嶋英治, 章執筆
アジア経済研究所 1980年01月
坂梨・林編『発展途上国の肥料産業』
村嶋英治, 章執筆
アジア経済研究所 1979年03月
『1978年次経済報告ータイ』(アジア経済研究所経済開発分析プロジェクトチーム編『アジア諸国の経済概況Ⅱ』1979年に再録)
村嶋英治
アジア経済研究所、144p. 1979年
『1977年次経済報告ータイ』
村嶋英治
アジア経済研究所、152p. 1978年
『アジア動向年表―1976年』pp.287-337
村嶋英治( 担当: 分担執筆, 担当範囲: タイの動向)
アジア経済研究所 1976年03月
『アジア動向年表―1975年』pp.275-322
村嶋英治( 担当: 分担執筆, 担当範囲: タイの動向)
アジア経済研究所 1975年03月
19世紀後半に於けるタイ王国の仏教ナショナリズム創出の実相の具体的且つ詳細な解明
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
村嶋英治
在タイ日本人の個人文書を初めて本格利用した近代国家移行期タイの社会構造の実態解明
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
村嶋 英治
近代タイ仏教社会における日本仏教者の知的営為:タイ地域研究の新展開と拡大に向けて
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
村嶋 英治
第2次世界大戦期日本・仏印・ベトナム関係研究の集大成と新たな地平
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
白石 昌也, 笹川 秀夫, 難波 ちづる, 菊池 陽子, 村嶋 英治, 湯山 英子, 岩月 純一, 古田 元夫, 早瀬 晋三, 立川 京一
タイ・インドシナ諸国間の国境政治の多面的体系的解明:一次資料の相互比較を通じて
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
村嶋 英治, 白石 昌也, 笹川 秀夫, 難波 ちづる, 伊藤 友美
20世紀タイ国における華僑華人社会の実相と役割-未利用中国語タイ語資料を用いて
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
村嶋 英治, 遠藤 元, 伊藤 友美, 安部 鶴代
東南アジア大陸部現代史に於ける共産主義運動の多面的根本的解明-タイを中心として-
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
村嶋 英治, 原 不二夫, 菊池 陽子, 伊藤 友美
第二次世界大戦期の在タイ邦人経営日刊新聞三紙(和、タイ、華文紙)に視る日タイ関係
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
村嶋 英治
アジア太平洋地域におけるヒトの移動と社会・文化変容
日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究促進費
研究期間:
平野 健一郎, 村嶋 英治, 小林 英夫, 後藤 乾一, 清水 元, 白石 昌也
アジアにおける社会・文化変容の実態と対応に関する国際比較研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業 国際学術研究
研究期間:
平野 健一郎, 村嶋 英治, 小林 英夫, 後藤 乾一, 白石 昌也
タイ近現代政治史における日本政治モデルをめぐる諸論争
日本学術振興会 科学研究費助成事業 一般研究(C)
研究期間:
村嶋 英治
タイ国における配布本の種類と利用法
村嶋英治
京都大学Global Collaborative Research(GCR)「タイ葬式本の資料共有化とその学術利用に係る実践的研究」(研究代表:日向伸介)、第2回研究会 村嶋英治報告要旨、2025年2月20日13-16時於京大稲盛財団記念館 1 - 7 2025年02月 [招待有り]
研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)
日本タイ学会2024年第一回定例研究会(2024年12月14日)「拙著『南北仏教の出会い』からみたタイの近代仏教:タマユット派を中心に」報告要旨及び資料
村嶋英治
1 - 22 2024年12月
2024年7月7日タイ学会(於大阪公立大学)「タイ王族貴族及び日本人の1903年シャム紙幣偽造事件から見えてくるもの」報告要旨
村嶋英治
1 - 6 2024年07月
研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)
ข้อมูลการบรรยาย เรื่อง ประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสยามก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 at the Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University on 15 May 2024
เออิจิ มูราชิมา, 村嶋英治
1 - 6 2024年05月 [招待有り]
2023年12月8日メコン地域研究会「近代タイにおける大乗仏教と『小乗仏教』」報告要旨
村嶋英治
1 - 4 2023年12月
2023年7月9日タイ学会(於大東文化大学)クルーバー・シーウィチャイ報告趣旨・資料
村嶋英治
1 - 6 2023年07月
研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)
การบรรยาย เรื่อง “ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสอบสวนครูบาศรีวิชัยที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2463(Historical Facts Concerning the Interrogation of Khruba Srivichai in Bangkok in 1920) " at Naresuan University on 12 Oct. 2022
Eiji Murashima, เออิจิ มูราชิมา
1 - 19 2022年10月 [招待有り]
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
การบรรยาย เรื่อง ความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาระหว่างญี่ปุ่นกับสยามในยุกใหม่วันที่๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว
Eiji Murashima, เออิจิ มูราขิมา
1 - 14 2022年09月 [招待有り]
Proclamations of Revolutionary Party Drafted by Luang Wichitwathakan(หลวงวิจิตรวาทการ) in Field Marshal Sarit ‘s Military Coup in 1958
村嶋英治
1 - 81 2022年03月
書評論文,書評,文献紹介等
『天田六郎氏遺稿、シャムの三十年など』にみる、1900-1930年代の在タイ日本人医業者
村嶋英治
日本タイ学会大会(2019年7月14日於日本女子大学)報告 1 - 32 2019年07月
2018年8月31日タイ国日本人会講演「戦前の日本人会の歴史を探して」
村嶋英治
2018年08月 [招待有り]
『堀井龍司憲兵中佐手記』(2017年3月刊行)をめぐって
村嶋英治
日本タイ学会大会(2017年7月8日於法政大学)報告 1 - 2 2017年07月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
岩本千綱の冒険的タイ移民事業(1894―1896)
村嶋英治
日本タイ学会大会(2016年7月3日於九州大学)報告 1 - 2 2016年07月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
明治期渡タイ日本人僧侶
村嶋英治
京都大学地域研究統合情報センター、共同研究個別ユニット(大澤広嗣代表)「仏教をめぐる日本と東南アジア地域―断絶と連鎖の総合的研究」第3回研究会報告 1 - 4 2015年11月 [招待有り]
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
เมื่ออาทิตย์อุทัยฉายแสงเหนือแดนสยาม
เออิจิ มูราชิมา ( ธนภาส เดชพาอุฒิกุล และ ปรียาภรณ์ กันทะลา สัมภาษ)
๗๐ปี วันสันติภาพไทย ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์(ภูริ ฟูวงศ์เจริญ บรรณาธิการ) 6 - 22 2015年08月 [招待有り]
その他
「タイにおける日本人社会の形成と変遷」報告資料
村嶋英治
2015年2月6日中部大学国際関係学学部・大学院国際人間学研究科共催「東南アジアの日本人社会の形成と変遷」シンポジウム 2015年02月 [招待有り]
早大アジア太平洋研究科における東南アジア(タイ)研究
村嶋英治
早稲田大学アジア研究機構第10回国際シンポジウム 2012年11月10-11日 78 - 81 2013年03月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
バンコクの日本人(14)美貌の初代公使夫人稲垣栄子(11)
村嶋英治
クルンテープ 19 ( 524 ) 8 - 11 2011年09月
タイにおける共産主義運動の初期時代(1930-1936):シャム共産党内におけるベトナム人幹部の役割を中心として
村嶋英治
東南アジア学会関東例会(2010年10月23日於上智大)報告 1 - 6 2010年10月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
タイ社会の危機:タイに何が生じているか
村嶋英治
早稲田大学アジア研究機構第42回アジアセミナー 1 - 42 2010年06月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
東南アジアの共産党再考研究会 報告
村嶋英治
南山大学アジア・太平洋研究センター主催研究会「東南アジアの共産党再考ー『未完に終わった国際協力』(原不二夫著)を読み解く 1 - 12 2009年06月 [招待有り]
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
18年間のタイの変化の中でタイから見た日本観はどう変わったか
村嶋英治
早稲田大学アジア太平洋研究センター国際関係公開講座 1 - 9 2007年11月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
เอกสารจดหมายเหตุไทยดีกว่าญี่ปุ่น
เออิจิ มูราชิมา Eiji Murashima
จดหมายข่าวจดหมายเหตุไทย 2 ( 1 ) 34 - 38 2005年08月 [招待有り]
速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要)
タイ近現代史の資料収集の経験から
村嶋英治
東南アジア史学会第273回関西例会・「東南アジア史研究で卒論・修論を書くための教育・研究工具の開発のための研究」研究会合同 1 - 23 2001年05月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
祭日と記念日の政治学:タイのケース
村嶋英治
京都大学東南アジア研究センター「支配の制度と文化」研究会報告 1 - 5 2000年06月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
タイ現代史と日本
村嶋英治
早稲田大学アジア太平洋研究センター国際関係公開講座 1 - 4 2000年06月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
バンコク初の高架鉄道
村嶋英治
『地理・地図資料』(帝国書院) ( 126 ) 24 - 24 1999年12月
「タイ」(分科会L『王様の政治学ーデモクラシーにおける王室』)
村嶋英治
日本政治学会大会報告(1998年10月4日於同志社大学) 1 - 1 1998年10月
タイ仏印紛争、タイの対ラーオ・クメール・ベトナム宣伝・共闘工作
村嶋英治
東南アジア史学会第57回大会『東南アジア史の中のタイ』シンポジウム於上智大学(1997年6月8日)報告 1 - 32 1997年06月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
日タイの歴史関係(1996年11月9日講演)
村嶋英治
『平成8年度成蹊大学公開講座講演録 アジアの心、アジアの力』 23 - 49 1997年03月
「シャム華人政治」研究報告セミナーに参加して
村嶋英治
『CAPS Newsletter (成蹊大学アジア太平洋研究センター)』 ( 52 ) 1 - 4 1996年07月
会議報告等
タイ研究とタイ国立公文書館
村嶋英治
『アジアの大都市 Newsletter( 大阪市立大学経済研究所)』 ( 2 ) 8 - 9 1995年11月
記事・総説・解説・論説等(その他)
タイ近代政治史における日本モデル
村嶋英治
東京大学政治史研究会報告 1 - 8 1992年11月 [招待有り]
研究発表ペーパー・要旨(全国大会,その他学術会議)
タイ争乱の背景と将来
村嶋英治
『社団法人アジア親善交流協会 研究会報告 第2号』 1 - 34 1992年06月
会議報告等
街の変貌で消えた政治の季節 世界の都市バンコク
村嶋英治
『アサヒグラフ』 ( 3516 ) 115 - 115 1989年11月
発展途上国の新潮流―タイの政治変動
村嶋英治
『貿易と産業』1984年4月号 40 - 42 1984年04月
タイー官僚政治の危機
村嶋英治
『現代の理論』 ( 199 ) 56 - 57 1984年03月
書評論文,書評,文献紹介等
東南アジアお国自慢の文化遺産(タイ)
村嶋英治
上智大学公開講座0134『東南アジアお国自慢の文化遺産』の「タイ」報告 1 - 2 2018年07月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
คำนิยม ในหนังสือ ๖๐ปี นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
เออิจิ มูราชิมา Eiji Murashima
16 - 19 2018年07月
バンコクにおける日本人商業の起源:名古屋紳商(野々垣直次郎、長坂多門)のタイ進出
村嶋英治
東南アジア学会関東例会(2015年4月25日於東京外国語大学)報告 1 - 3 2015年04月
講演資料等(セミナー,チュートリアル,講習,講義他)
バンコクの日本人(4)美貌の初代公使夫人稲垣栄子(1)
村嶋英治
『クルンテープ(泰国日本人会会報)』 18 ( 514 ) 20 - 23 2010年11月
書評 小林秀明著『クーデターとタイ政治 日本大使の1035日』を読む (特集 タイのゆくえ)
村嶋 英治, 山辺 福二郎
『クルンテ-プ(泰国日本人会会報)』 18 ( 510 ) 13 - 15 2010年07月
村嶋 英治, 大野 浩
『タイ国情報』 44 ( 4 ) 87 - 95 2010年07月
アジア太平洋研究科における博士後期課程内規およびAO内規等の成立
村嶋英治
『早稲田大学大学院アジア太平洋研究科創設10周年記念誌』 67 - 68 2008年10月
記事・総説・解説・論説等(その他)
偏しない国民、タイ
村嶋英治
『新鐘』(早稲田大学学生部) ( 67 ) 54 - 54 2002年12月
記事・総説・解説・論説等(その他)
村嶋 英治
『東南アジア研究』 36 ( 2 ) 255 - 256 1998年09月
プロジェクト現地調査報告・インドシナ半島研究
村嶋英治
『CAPS Newsletter(成蹊大学アジア太平洋研究センター)』 ( 54 ) 6 - 6 1997年01月
倉沢 愛子, 村嶋 英治
重点領域研究総合的地域研究成果報告書シリーズ : 総合的地域研究の手法確立 : 世界と地域の共存のパラダイムを求めて ( 18 ) 29 - 37 1996年05月
祝・プミポン国王在位50周年 スペシャルインタビュー(中)
村嶋英治
『バンコク週報』 1996年03月
玉田 芳史, 赤木 攻, 村嶋 英治, 橋本 卓, 池本 幸生
重点領域研究総合的地域研究成果報告書シリーズ : 総合的地域研究の手法確立 : 世界と地域の共存のパラダイムを求めて ( 7 ) 72 - 78 1995年03月
新所員の紹介 文学部教授村嶋英治
村嶋英治
『CAPS Newsletter (成蹊大学アジア太平洋研究センター)』 ( 45 ) 4 - 5 1994年10月
その他
คุยกับสมาชิก ในวารสาร สาส์นจากสมาคม ปีที่๑ ฉบับที่๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗
ชัยชนะ อิงคะวัต
5 - 6 1994年07月
アジアと私
村嶋英治
『CAPS Newsletter (成蹊大学アジア太平洋研究センター)』 ( 43 ) 5 - 5 1994年04月
その他
玉田 芳史, 赤木 攻, 村嶋 英治, 橋本 卓
重点領域研究総合的地域研究成果報告書シリーズ : 総合的地域研究の手法確立 : 世界と地域の共存のパラダイムを求めて ( 1 ) 74 - 81 1994年03月
村嶋 英治
『国際協力』(『41人の英雄たち:民族の誇り』国際開発ジャーナル社、1993年、86-91頁に再録) 1990年9月号 ( 425 ) 34 - 35 1990年09月
タイで急速に進む民高官低の風潮
村嶋英治
『カントリーリスク情報』 ( 211 ) 9 - 12 1990年07月
その他
タイの言論、アジア時評
村嶋英治
『北海道新聞』(夕刊) 1989年12月
คำนิยม ในหนังสือเกียวโตใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
เออิจิ มูราชิมา, 村嶋英治
3 - 4 1989年01月
その他
タイ (日本における発展途上地域研究1978〜85--地域編〔含 文献リスト〕) (アジア経済研究所『発展途上国研究1978~85 日本における成果と課題』1986年12月212-218頁再録)
村嶋 英治, 末廣 昭
『アジア経済』 27 ( 9-10 ) 212 - 218 1986年10月
ความคิดชาตินิยมสองกระแสในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในแง่เปรียบเทียบ
Eiji Murashima, โสภิวรรณ บริบูรณ์
นิตยสารตะวัน(สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 37 - 40 1985年05月
記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
「第四次プレーム内閣主要閣僚28人の経歴書」
村嶋英治
『国際開発ジャーナル』 第324号 20 - 27 1983年07月
タイの新聞(海外だより52)
村嶋英治
アジア経済研究所『所内報』 ( 134 ) 8 - 8 1981年11月
2015年
Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API in January 14, 2026, via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .