学歴
-
-1986年
大阪大学 人間科学研究科 社会学
-
-1983年
早稲田大学 文学部 社会学専攻
2026/02/25 更新
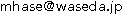
大阪大学 人間科学研究科 社会学
早稲田大学 文学部 社会学専攻
日本映像学会 機関誌『映像学』編集委員
日本社会学会 研究活動委員
日本映像学会
日本社会学会
社会学(含社会福祉関係)
シミュレーションとしての山田太一ドラマ
長谷正人
ユリイカ(2024年4月号 特集:山田太一) 56 ( 5 ) 186 - 193 2024年04月
ヴァナキュラー・モダニズムとしてのクレイジーキャッツ
長谷正人
ユリイカ(2024年2月号 特集クレイジーキャッツの時代) 56 ( 2 ) 77 - 83 2024年02月
労働としての映画─『勝手に逃げろ/人生』におけるゴダールの転回をめぐって
長谷正人
ユリイカ(2023年1月臨時増刊号 総特集◎ジャン=リュック・ゴダール─1930-2022) 55 ( 2 ) 519 - 525 2022年12月
「幼年期」の映画、あるいは記号化する日常と「身体」──極私的大林宣彦論
長谷正人
ユリイカ 総特集大林宣彦1939-2020 52 ( 10 ) 93 - 103 2020年08月
津波映像と『アナ雪』─視覚文化における「音声化」の諸問題
長谷正人
群像 75 ( 6 ) 308 - 315 2020年06月
坪内祐三における「死にがい」の探求と連合赤軍─『一九七二」を読み直す
長谷正人
ユリイカ 総特集坪内祐三1958-2020 52 ( 5 ) 243 - 254 2020年04月
自己、写真、ファッション─アウラの凋落とファッション文化
長谷正人
Fasion Talks... ( 10 ) 14 - 19 2019年12月
複製技術時代における思考の可能性─ベンヤミンの複製芸術論を読み直す
長谷正人
早稲田大学大学院文学研究科紀要 64 805 - 820 2019年03月
「社会実験」としての映画─『ハッピーアワー』について考える
長谷正人
ユリイカ2018年9月号(特集 濱口竜介) 50 ( 12 ) 268 - 275 2018年09月
聡明な作家、是枝裕和
長谷正人
KAWADE夢ムック文藝別冊是枝裕和 124 - 128 2017年09月
反=接吻映画としての『晩春』─占領政策と小津安二郎
長谷正人
ユリイカ11月臨時増刊号 45 ( 15 ) 175 - 187 2013年10月
お茶の間に仕掛けたメディア的“罠”
長谷正人
寺山修司の迷宮世界(洋泉社MOOK) 80 - 83 2013年05月
「パーソナルな文化」としてのテレビドラマ─山田太一とサリンジャー
長谷正人
kAWADE夢ムック文藝別冊総特集山田太一 204 - 211 2013年05月
ドラマご馳走主義の作家
長谷正人
文藝別冊 木皿泉 物語る夫婦の脚本と小説(河出書房新社) 133 - 139 2013年04月
社会学という不自由
長谷正人
思想地図 ( 5 ) 131 - 147 2010年03月
ビートたけし(21世紀の冒険者48)
長谷正人
daiaries(ダイアリーズ) ( 1 ) 108 2008年08月
テレビはジャーナリズム論では語れない(書評ヒューマイルズ『アルジャジーラ 報道の戦争』光文社)
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 12 ) 146 - 147 2006年03月
映画、小津、時間(3)
長谷正人
UP/東京大学出版会 ( 388 ) 38 - 42 2005年02月
アニメーションという思想ー宮崎駿試論
長谷正人
早稲田大学大学院文学研究科紀要 第50輯第1分冊 83 - 96 2005年02月
映画、小津、時間(2)
長谷正人
UP/東京大学出版会 ( 387 ) 46 - 50 2005年01月
心霊写真は語る/(第2章「ヴァナキュラー・モダニズムとしての心霊写真」)
一柳廣孝編
青弓社 63 - 87 2004年08月
日本映画とナショナリズム1931−1945/(第10章「日本映画と全体主義:津村秀夫の映画批評をめぐって」)
岩本憲児編
森話社 2004年06月
アフォーダンス理論のパフォーマンス
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 7 ) 76 - 78 2004年05月
「痕跡」と「指差し」─写真の訳の分からなさをめぐって
長谷正人
木野評論/青幻社 ( 35 ) 2004年03月
現代若者考⑧ 若者の寂しさ
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 45 ) 2004年02月
映画にとって細部とは何か;リュミエールと宮崎駿をめぐって
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 6 ) 91 - 94 2004年02月
二0世紀の映像文化:「エジソン的回帰」をめぐって
長谷正人
映画学/映画学研究会(早稲田大学文学部演劇映像研究室内) ( 16 ) 2002年12月
運動雑記帳1−14
長谷正人
ATHRA(毎日コミュニケーションズ) 10号から25号まで連載 2002年02月
現代若者考⑥ストリート・ミュージシャン
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 43 ) 58 - 59 2001年12月
物語、あるいは映画の柔らかい肌
長谷正人
物語の風俗(現代風俗研究会年報)/河出書房新社 ( 23 ) 114 - 125 2001年09月
現代若者考⑤メル友
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 42 ) 46 - 47 2001年01月
<観客>のゆくえ(森直人編『21世紀/シネマX』)
長谷正人
フィルムアート社 130 - 133 2000年12月
日本映画と全体主義:津村秀夫をめぐって
長谷正人
映像学/日本映像学会 ( 63 ) 1999年12月 [査読有り]
映画哲学1〜10
長谷正人
ロゴスドン/ヌース出版会 33号から42号まで連載 1999年07月
社会福祉辞典(「遊び」「ダブルバインド」「無意識」など10項目を執筆)
庄司洋子, 木下, 康仁, 武川, 正吾, 村正之
弘文堂 1999年05月
The Origins of Censorship:Police and Motion Pictures in the Tisho period(「検閲の誕生」の英訳)
Hase Masato
Review of Japanese Culture and Society/城西国際大学 ( 10 ) 14 - 23 1998年12月
リュミエール兄弟のアルケオロジー
長谷正人
CineMagaziNet!(http://www.cmn.hs.h.kyoto-u.ac.jp/NO2/Default2.htm) ( 2 ) 1998年06月
Cinemaphobia in Taisho Japan :Zigomar,Delinquent Boys and Somnambulism
Masato Hase
ICONICS ( 4 ) 87 - 101 1998年03月 [査読有り]
現代若者考②カラオケ
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 39 ) 82 - 83 1998年03月
映画観客の「笑い」について
長谷正人
現代風俗学研究 ( 4 ) 74 - 76 1998年03月
現代若者考①プリクラ
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 38 ) 82 - 83 1997年09月
学問の世界地図〔文化の社会学〕 文化=意味づけの体系をひっくり返す魅力
長谷正人
別冊宝島『学問の鉄人 大学教授ランキング』 ( 322 ) 120 - 121 1997年07月
リュミエールの考古学
長谷正人
映像学(日本映像学会) 55号 1996年11月 [査読有り]
メディアとしての映画館
長谷正人
現代風俗学研究/社団法人現代風俗研究会東京の会 ( 2 ) 1996年04月
ヴァーチャルじいさん笠智衆
長谷正人
imago(イマーゴ)/青土社 5 ( 10 ) 187 1994年01月
ユートピア世界としての「男はつらいよ」
長谷正人
『男はつらいよ 寅次郎の告白』劇場用パンフレット 1991年12月
行為の意図せざる結果 (2)
長谷正人
千葉大学教養部研究報告 ( A-22 ) 173 - 202 1990年03月
ダブル・バインドへのシステム論的アプローチ
長谷正人
社会学評論(日本社会学会) 40 ( 3 ) 310 - 324 1989年12月 [査読有り]
行為の意図せざる結果 (1)
長谷正人
千葉大学教養部研究報告 ( A-21 ) 107 - 135 1989年03月
書評 作田啓一・井上俊編『命題コレクション・社会学』
長谷正人
ソシオロジ 32 ( 1 ) 98 - 101 1987年05月
スペクタクル後 AFTER THE SPACTACLE 第14回恵比寿映像祭コンセプトブック
長谷正人( 担当: 分担執筆, 担当範囲: 映像とスペクタクル)
東京都写真美術館 2022年02月
大テレビドラマ博覧会 : テレビの見る夢
長谷正人( 担当: 分担執筆, 担当範囲: <孤独>のドラマ─山田太一の笠智衆三部作をめぐって)
早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2017年05月 ISBN: 9784948758179
作田啓一vs.見田宗介(第2章見田宗介における「相乗性」という限界─『近代日本の心情の歴史』を読み直す)
奥村隆編( 担当: 分担執筆)
弘文堂 2016年11月
ひとびとの精神史第7巻 終焉する昭和/1980年代(「宮崎駿─職人共同体というユートピア」担当)
長谷正人, 杉田敦編( 担当: 共著)
岩波書店 2016年02月
全訂新版 現代文化を学ぶ人のために(第7章映像文化の三つの位相─見ること、撮ること、撮られること)
井上俊編
世界思想社 2014年08月
イヌジン──映画『イヌミチ』への手紙
長谷正人( 担当: 分担執筆, 担当範囲: 万田邦敏のカントクミチ)
映画美学校 2014年03月
横断する映画と文学(「第8章長谷川伸と股旅映画─映画を見ることと暮らしの倫理性をめぐって」を執筆)
十重田裕一編
森話社 2011年07月
社会学ベーシックス別巻 社会学的思考(第13章物語と社会学的想像力 厚東洋輔『社会認識と想像力』)
井上俊, 伊藤公雄編
世界思想社 2011年05月
『日本映画は生きている 第3巻観る人、作る人、掛ける人』(「日本映画のポストモダン」を執筆)
黒沢清, 四方田犬彦, 吉見俊哉, 李鳳宇編
岩波書店 2010年09月
大衆文化とメディア(叢書 現代のメディアとジャーナリズム4)
吉見俊哉, 土屋礼子編, 第, 章 大正期日本における映画恐怖症─ジゴマ, 夢遊病, ごっこ遊び
ミネルヴァ書房 2010年08月
社会学ベーシックス7 ポピュラー文化(第3章ポピュラー文化の神話学、バルト『現代社会の神話』を執筆)
井上俊, 伊藤公雄編
世界思想社 2009年05月
よくわかるメディア・スタディーズ
伊藤守編
ミネルヴァ書房 2009年03月
『新たな地平を拓く研究者たち』(「オウムと震災後のメディア社会の中で息苦しさを超えて」)
日経BP企画, 大学取材班
日経BP 2008年12月
社会学ベーシック1 自己・他者・関係(23章「メタ・コミュニケーション(ベイトソン『精神の生態学』)を執筆)
井上俊, 伊藤公雄編
世界思想社 2008年09月
『明るい部屋』の秘密─ロラン・バルトと写真の彼方へ(「写真、バルト、時間」を再録)
青弓社編集部
青弓社 2008年08月
女優 山口百恵(第2章 「『赤い』シリーズ──百恵神話の成立」を執筆)
四方田犬彦
ワイズ出版 2006年07月
私の愛した地球博(コラム「大阪万博の記憶から愛知万博を考える」を執筆)
加藤晴明, 岡田朋之, 小川明子
リベルタ出版 2006年07月
世界と僕たちの、未来のために 森達也対談集 (鼎談「われわれはいまだに<オウム事件>の渦中にいる」の再録)
森達也
作品社 2006年01月
自己と他者の社会学(第10章「ヴァーチャルな他者とのかかわり」を執筆)
井上俊, 船津衛
有斐閣 2005年12月
社会文化理論ガイドブック(執筆項目は「アウラの凋落」と「物語批判」)
大村英昭, 宮原浩二郎, 名部圭一
ナカニシヤ出版 2005年06月
心霊写真は語る/(第2章「ヴァナキュラー・モダニズムとしての心霊写真」)
一柳廣孝
青弓社 2004年08月
日本映画とナショナリズム1931−1945/(第10章「日本映画と全体主義:津村秀夫の映画批評をめぐって」)
岩本憲児編
森話社 2004年06月
電子メディア文化の深層/伊藤守・小林宏一・正村俊之編(第2章「20世紀の映像文化とメロドラマ的想像力」)
早稲田大学出版 2003年09月
情報化と文化変容(「『絶対速度』の移動体験──情報化社会の映画をめぐって」を執筆)
正村俊之編
ミネルヴァ書房 2003年09月
アンチ・スペクタクル-沸騰する映像文化の考古学〈アルケオロジー〉
長谷 正人(編訳, 中村 秀之(編訳, 中村, 秀之( 担当: 共編者(共編著者))
東京大学出版会 2003年06月 ISBN: 4130802038
文化社会学への招待(第一章「遊び」をめぐる「離脱」と「拘束」;『丹下左膳余話・百万両の壷』をめぐって)
富永茂樹他編
世界思想社 2002年05月
臨床社会学を学ぶ人のために(「セルフヘルプグループの調査実習から:「個別的な苦しみ」をめぐる社会学の可能性」)
大村英昭編
世界思想社 2000年10月
新版・現代文化を学ぶ人のために(第7章「映像化社会の成立と映画の変容」を執筆)
井上俊
世界思想社 1998年11月
現代社会学 第8巻 文学と芸術の社会学(「overview 文学と芸術の社会学」を執筆)
井上俊, 上野千鶴子, 大澤真幸, 見田宗介, 吉見俊哉編
岩波書店 1996年09月
社会学のすすめ (第2章「遊戯としてのコミュニケーション」を執筆)
大澤真幸
筑摩書房 1996年05月
組織とネットワークの理論(『モグラとヘビ・・管理社会の歩き方』を執筆)
宮本孝二, 森下伸也, 君塚大学編
新曜社 1994年04月
「自撮り」のメディア文化史
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
長谷 正人, 菊池 哲彦, 前川 修, 加藤 裕治, 川崎 佳哉, 松谷 容作, 大久保 遼, 増田 展大, 角田 隆一
メディア文化における「孤独」の系譜
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
長谷 正人, 菊池 哲彦, 前川 修, 加藤 裕治, 川崎 佳哉, 松谷 容作, 大久保 遼, 増田 展大, 角田 隆一
デジタル化時代における映像文化の日常的変容
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
長谷 正人, 菊池 哲彦, 前川 修, 加藤 裕治, 松谷 容作, 大久保 遼, 増田 展大, 角田 隆一
テレビドラマとポストモダン社会
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
長谷 正人
テレビ文化のメディア史的考察
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
長谷 正人, 難波 功士, 北田 暁大, 丹羽 美之
ドキュメンタリー・バラエティ番組のメディア史的考察
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
長谷 正人
1920-40年代日米における映画検閲の比較社会学的研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
長谷 正人, 加藤 幹郎
クイズ形式の文化についての歴史的・比較文化的研究〜テレビ番組を中心に〜
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
小川 博司, 石田 佐恵子, 長谷 正人, 川崎 賢一, 河原 和枝, 遠藤 知巳, 岡田 朋之
映画館の社会的機能に関する研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
長谷 正人
芸術表現におけるイデオロギー:全体主義と文化
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
多木 浩二, 田中 日佐夫, 川端 香男里, 長谷 正人, 佐藤 和夫, 若桑 みどり, 大室 幹雄
映画俳優、その可能性の中心
長谷正人
文藝春秋 103 ( 12 ) 85 - 87 2025年12月
担当区分:筆頭著者
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
なぜ「暗い」「地味」なのに面白い? 朝ドラ『ばけばけ』が観る者を惹きつけるワケ。メディア研究の専門家がわかりやすく解説
長谷正人
映画ちゃんねる(https://eigachannel.jp/drama/169083/) 2025年10月
担当区分:筆頭著者
記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
「口語の文化」と「変身の文化」──放送100年と民主主義の可能性
長谷正人
中央公論2025年3月号 139 ( 4 ) 146 - 153 2025年03月
その他
書評 北村洋『淀川長治─「映画の伝道師」と日本のモダン』名古屋大学出版会
長谷正人
図書新聞2025年2月22日 ( 3676 ) 2025年02月
書評論文,書評,文献紹介等
ビジネスは演劇の一種にすぎない
長谷正人
フリースタイル ( 62 ) 9 - 11 2025年01月
[鼎談]山田太一の季節
長谷正人, 頭木弘樹, 岡室美奈子
ユリイカ(2024年4月号 特集:山田太一) 56 ( 5 ) 162 - 177 2024年04月
その他
山田太一ドラマとは何だったのか~ディスカッション・ドラマと底流の孤独と
長谷正人
GALAC 2024年04月
その他
ジャニーズ性加害問題に覚える違和感、そもそも日本のアイドルはいつから「性的に消費」されはじめたのか。
長谷正人
現代ビジネス(https://gendai.media/articles/-/118596) 2023年11月
その他
「絶望」パスタとテレビの希望
長谷正人
フリースタイル ( 57 ) 13 - 15 2023年10月
その他
「大人こそ、やるべきよ」
長谷正人
フリースタイル ( 55 ) 5 - 7 2023年04月
On Curling’s Ritualistic Culture and its Social Media Fan Culture
Masato Hase (translated by Xavi Sawada)
Discuss Japan:Japan Foreign Policy Forum ( 71 ) 2022年08月
記事・総説・解説・論説等(その他)
時評:儀礼的文化としてのカーリングとSNSを媒介したファン文化
現代スポーツ評論 ( 46 ) 145 - 152 2022年05月
土着と記号の狭間で─前川修『イメージのヴァナキュラー ─写真論講義 実例編』を読んで
長谷正人
UP 49 ( 8 ) 44 - 48 2020年08月
レヴュー 北浦寛之『テレビ成長期の日本映画─メディア間交渉のなかのドラマ』
長谷正人
映像学 ( 102 ) 212 - 215 2019年07月
空虚な自己宣伝としての政治運動(草森紳一『絶対の宣伝 ナチス・プロパガンダ3扇動の方法』解説)
長谷正人
2016年05月
記事・総説・解説・論説等(その他)
大量消費社会とパーソナル文化
長谷正人
世界思想 ( 42 ) 18 - 22 2015年04月
お茶の間に仕掛けたメディア的“罠”
長谷正人
寺山修司の迷宮世界(洋泉社MOOK) 80 - 83 2013年05月
ドラマご馳走主義の作家
長谷正人
文藝別冊 木皿泉 物語る夫婦の脚本と小説(河出書房新社) 133 - 139 2013年04月
テレビ時代の映画──木下惠介のテレビ作品を歴史的に位置づける
長谷正人
NFCニューズレター ( 105 ) 3 - 5 2012年10月
日常的体験としてのテレビドキュメンタリー
長谷正人
neoneo ( 1 ) 30 - 31 2012年09月
書評 蓮實重彦『映画時評 2009−2011』
長谷正人
映画芸術 ( 440 ) 149 - 150 2012年07月
概観2011年(映像)
長谷正人
文藝年鑑2012 130 - 133 2012年06月
映像のフィジカル─飼いならせない野性の映像のために(対談)
諏訪敦彦, 長谷正人
第4回恵比寿映像祭「映像のフィジカル」カタログ 12 - 29 2012年02月
敗者の想像力──脚本家山田太一(第16回)キツネに化かされる話
長谷正人
GALAC 166 36 - 39 2011年03月
メディアはなぜあるのか
長谷正人
マス・コミュニケーション研究 ( 78 ) 3 - 18 2011年01月
敗者の想像力──脚本家山田太一(第13回)「想い出づくり」、キャラが立つこととリアリズム
長谷正人
GALAC ( 162 ) 36 - 39 2010年11月
敗者の想像力──脚本家山田太一(第11回)輝きたいの
長谷正人
GALAC ( 160 ) 36 - 40 2010年09月
画面が切り開く「遊動空間」の可能性(書評・中村秀之『瓦礫の天使たち』せりか書房』)
長谷正人
図書新聞 2983 8 2010年09月
「ヴァナキュラー・イメージ」と「メディア文化」─シミュラークルとしての「ルー大柴」をめぐって
長谷正人
SITE/ZERO ZERO/SITE ( 3 ) 124 - 133 2010年06月
敗者の想像力─脚本家山田太一(第九回)不機嫌なドラマ
長谷正人
GALAC ( 157 ) 38 - 41 2010年06月
敗者の想像力ー脚本家山田太一(第八回)敗者の逆転劇
長谷正人
GALAC ( 156 ) 36 - 39 2010年05月
敗者の想像力─脚本家山田太一(第七回)不条理劇が終わった後を描くドラマ
長谷正人
GALAC ( 155 ) 36 - 39 2010年04月
敗者の想像力─脚本家山田太一(第五回)敗戦国日本の旅路
長谷正人
GALAC ( 153 ) 36 - 39 2010年02月
『あいのり』は「やらせ」か─テレビが作り出す純粋な恋愛
長谷正人
新鐘 ( 76 ) 39 - 40 2009年11月
書評・上野昴志『紙上で夢みる 現代大衆小説論』(清流出版)
長谷正人
キネマ旬報 ( 1546 ) 154 2009年11月
敗者の想像力─脚本家 山田太一(第一回)
長谷正人
GALAC ( 148 ) 32 - 35 2009年09月
ジオラマ化する世界3(「モネの庭」)
長谷正人
写真空間 ( 3 ) 137 - 145 2009年05月
「表話」としての映画批評─神話化の危険には注意すべき(書評・蓮實重彦『映画論講義』東大出版)
長谷正人
図書新聞 ( 2900 ) 2009年01月
虚構とアイロニーの80年代(対談)
大澤真幸, 長谷正人
大航海 ( 68 ) 72 - 93 2008年09月
ジオラマ化する世界2(『父親たちの星条旗、あるいはジオラマの内と外)
長谷正人
写真空間 ( 2 ) 169 - 179 2008年09月
ビートたけし(21世紀の冒険者48)
長谷正人
daiaries(ダイアリーズ) ( 1 ) 108 2008年08月
想像力の「飛躍」を迫る(万田邦敏監督『接吻』評)
長谷正人
図書新聞 ( 2826 ) 8 2008年03月
ジオラマ化する世界 1(カール・エイクリー/杉本博司の生態ジオラマ)
長谷正人
写真空間/青弓社 ( 1 ) 215 - 224 2008年03月
社会学から見た70年代注目の理由(インタビュー)
長谷正人
宣伝会議 ( 737 ) 34 - 35 2008年03月
複製技術という問題と高級/大衆芸術としての映画─竹峰義和『アドルノ、複製技術へのまなざし』書評
長谷正人
表象 ( 02 ) 281 - 288 2008年03月
機械的反復としてのエックス線写真
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 15 ) 88 2007年12月
分野別研究動向(文化)──「ポストモダンの社会学」から「責任と正義の社会学」へ──
長谷正人
社会学評論 (日本社会学会) 57 ( 3 ) 615 - 633 2006年12月
創造とは何か?──フーコー、キアロスタミ、デリダ
長谷正人
Mobile Society Review(未来心理)/モバイル社会研究所 ( 8 ) 4 - 11 2006年12月
トリックスターになった前衛写真家『カメラになった男──写真家 中平卓馬』
長谷正人
美術手帖/美術出版社 58 ( 887 ) 170 - 171 2006年10月
マンガ研究と映画研究
長谷正人
日本映像学会会報(展望) ( 136 ) 3 2006年10月
テレビはジャーナリズム論では語れない(書評ヒューマイルズ『アルジャジーラ 報道の戦争』光文社)
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 12 ) 146 - 147 2006年03月
<表現>としての犯罪対策へ:われわれは、いまだに<オウム事件>の渦中にいる
大澤真幸, 長谷正人, 森達也
劇場文化(財団法人静岡県舞台芸術センター) ( 8 ) 84 - 124 2005年05月
写真、バルト、時間:『明るい部屋』を読み直す
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 10 ) 99 - 103 2005年04月
書評・阿部嘉昭『68年の女を探して:私説・日本映画の60年代』(論創社)
長谷正人
図書新聞 ( 2697 ) 2004年10月
「切り返し」の想像力の発見:100年前の映画をめぐって
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 8 ) 121 - 123 2004年07月
日本映画とナショナリズム1931−1945/(第10章「日本映画と全体主義:津村秀夫の映画批評をめぐって」)
岩本憲児編
森話社 2004年06月
アフォーダンス理論のパフォーマンス
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 7 ) 76 - 78 2004年05月
ブックデザインになにが可能か
ミルキイ・イソベ, 祖父江慎, 長谷正人, 鈴木一誌, 戸田ツトム
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 7 ) 164 - 173 2004年05月
映画にとって細部とは何か;リュミエールと宮崎駿をめぐって
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 6 ) 91 - 94 2004年02月
レイアウトとしての映画;時間的想像力の可能性をめぐって
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 ( 5 ) 106 - 109 2003年10月
intermedia——メディアと芸術の相関を思考する (第1巻5章「記憶と忘却の経験としての映画」)
早稲田大学メディアデザイン研究室, 映像コミュニケーション研究所
トランスアート社 2003年10月
複製というアウラ;ベンヤミン、笠智衆、グールド
長谷正人
d/sign(デザイン)/太田出版 no.4 68 - 73 2003年05月
クイズ文化の社会学(コラム「テレビ番組の『形式』としてのクイズ」を執筆)
石田佐恵子, 小川博司編
世界思想社 108 - 109 2003年03月
テレビ世界の生態学的観察者;ナンシー関の倫理をめぐって
長谷正人
トリビュート特集 ナンシー関/河出書房新社 2003年03月
テレビ出演という謎:『未来日記』試論
長谷正人
現代風俗学研究/社団法人現代風俗研究会東京の会 ( 9 ) 20 - 25 2003年03月
書評・荻野昌弘編著『文化遺産の社会学:ルーヴル美術館から原爆ドームまで』
長谷正人
社会学評論(日本社会学会) 53 ( 4 ) 2003年03月
夢としての資本主義──ハリウッド映画の魅力とは何だったのか
長谷正人
早稲田学報 2003年03月
テレビは外延化しつづけるフレームである(鈴木一誌によるインタビュー)
長谷正人
d/sign(デザイン)/丸善 ( 3 ) 54 - 63 2003年01月
情報学辞典
吉見俊哉他編
弘文堂 2002年06月
「文化」のパースペクティヴと日本社会学のポストモダン的変容
長谷正人
文化と社会 ( 3 ) 56 - 74 2002年02月
担当区分:筆頭著者
カメラの存在論
長谷正人
「写真の会」会報 ( 50 ) 2 - 10 2001年09月
物語、あるいは映画の柔らかい肌
長谷正人
物語の風俗(現代風俗研究会年報)/河出書房新社 ( 23 ) 114 - 125 2001年09月
書評・黒沢清『映画はおそろしい』
長谷正人
文学界 2001年5月号 313 - 315 2001年04月
伊奈正人『サブカルチャーの社会学』(世界思想社)
長谷正人
ソシオロジ/社会学研究会 ( 140 ) 2001年02月
<観客>のゆくえ(森直人編『21世紀/シネマX』)
長谷正人
フィルムアート社 130 - 133 2000年12月
チーム・プレイのドキュメント(ハワードホークス論)
長谷正人
月蛙(子供社) ( 2 ) 85 - 91 2000年04月
新・社会人のための基礎知識101(65「生きがいの探求」を執筆)
樺山紘一編
新書館 154 - 155 2000年04月
現代若者考④ケータイ
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 41 ) 98 - 99 2000年03月
現実構成主義から遠く離れて
長谷正人
ソシオロジ/社会学研究会 ( 137 ) 2000年02月
テクノロジーの経験としての映画:戦争、全体主義、そして生命のリズム
長谷正人
月蛙/子供社 ( 1 ) 80 - 93 1999年10月
映画哲学1〜10
長谷正人
ロゴスドン/ヌース出版会 33号から42号まで連載 1999年07月
社会福祉辞典(「遊び」「ダブルバインド」「無意識」など10項目を執筆)
庄司洋子, 木下, 康仁, 武川, 正吾, 村正之
弘文堂 1999年05月
現代若者考③コンビニ
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 40 ) 98 - 99 1999年03月
『学問の鉄人が贈る14歳と17歳のBOOKガイド』(蓮實重彦『監督小津安二郎』の紹介を執筆)
河合塾編
メディアファクトリー 25 1999年01月
The Origins of Censorship:Police and Motion Pictures in the Tisho period(「検閲の誕生」の英訳)
Hase Masato
Review of Japanese Culture and Society/城西国際大学 ( 10 ) 14 - 23 1998年12月
亜細亜 映画 研究; 歴史 美学 正体性 産業(The Identity of Japanese Cinemaを執筆)
韓国映画学会編
Good Living(Korea) 273 - 288 1998年11月
リュミエール兄弟のアルケオロジー
長谷正人
CineMagaziNet!(http://www.cmn.hs.h.kyoto-u.ac.jp/NO2/Default2.htm) ( 2 ) 1998年06月
書評 上野昴志『映画全文 1992−1997』
長谷正人
映画館へ行こう!(えとしっく) ( 14 ) 131 - 133 1998年06月
書評 矢谷慈國著『賢治とエンデ : 宇宙と大地からの癒し』
長谷正人
社会学評論/日本社会学会 49 ( 1 ) 138 - 140 1998年06月
現代若者考②カラオケ
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 39 ) 82 - 83 1998年03月
映画観客の「笑い」について
長谷正人
現代風俗学研究 ( 4 ) 74 - 76 1998年03月
Cinemaphobia in Taisho Japan :Zigomar,Delinquent Boys and Somnambulism
Masato Hase
ICONICS 4 ( 4 ) 87 - 101 1998年03月 [査読有り]
社会学文献辞典(クラカウアー『カリガリからヒットラーまで』の項を執筆)
見田宗介他編
弘文堂 1998年02月
現代若者考①プリクラ
長谷正人
カルチャーちば/千葉市文化振興財団 ( 38 ) 82 - 83 1997年09月
<シリーズ対談=人間と看護を考える>こころとからだ 遊びと効用(1)(2)
藤村正之, 長谷正人
看護展望(メチ”カルフレンド社) 1997年07月
現実性のスペクタクルとドキュメンタリー映画
エリザベス・カウイ
Documentary Box(山形国際ドキュメンタリー映画祭事務局) ( 10 ) 1 - 8 1997年06月
社会学小事典・新版(「意図せざる結果」「ベートソン」「ミミクリー」を執筆)
濱嶋朗, 竹内郁郎, 石川晃弘
有斐閣 1997年01月
リュミエールの考古学
長谷正人
映像学(日本映像学会) 55号 1996年11月
映像のオントロギー(1)−(40)
長谷正人
Internet photo Magazine(http://www.ipm.jp/ipmj/back.html)に毎月連載 1996年08月
ブックガイド 20世紀のアート&テクノロジー50冊(ベイトソン『精神の生態学』の項目を執筆)
長谷正人
intercommunication/NTT出版 ( 17 ) 1996年07月
眼の規律
長谷正人
imago(イマーゴ)/青土社 5 ( 10 ) 284 - 285 1994年09月
第二次世界大戦下のアメリカ映画と映画の情報メディア化;『われらなぜ戦うか』をめぐって
長谷正人
平成5 年度科学研究費補助金( 総合研究A) 研究成果報告書『芸術表現におけるイデオロギー;全体主義と文化』 41 - 54 1994年03月
ヴァーチャルじいさん笠智衆
長谷正人
imago(イマーゴ)/青土社 5 ( 10 ) 187 1994年01月
フーコー・ドゥルーズ・ユーモア
長谷正人
ブリーフサイコセラピー研究/亀田書店 ( 2 ) 1993年07月
新社会学辞典
森岡清美, 塩原勉, 本間康平編
有斐閣 1993年02月
視姦された映画とマゾヒズムのまなざし・・・バルト/ ドゥルーズの映画鑑賞
長谷正人
imago(イマーゴ)/青土社 3 ( 12 ) 188 - 196 1992年10月
ユートピア世界としての「男はつらいよ」
長谷正人
『男はつらいよ 寅次郎の告白』劇場用パンフレット 1991年12月
言語行為論、現実構成主義、家族療法
長谷正人
現代のエスプリ(至文堂) ( 287 ) 41 - 48 1991年06月
映像文化の比較社会学的研究
アメリカ なし
商学学術院 商学部
文学学術院 大学院文学研究科
附属機関・学校 グローバル・エデュケーション・センター
2014年
2011年
2006年
2000年
Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API in February 23, 2026, via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .