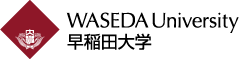共同研究・競争的資金等の研究課題
共同研究・競争的資金等の研究課題
-
民事訴訟審理における裁判官の積極性と当事者行為の規律の関係に関する研究
研究期間:
2018年04月-2021年03月概要を見る
本研究は「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」という観点から、この裁判官の積極性と当事者行為の規律の関係を明らかにすることを目的とする。昨年までの研究から、わが国では、裁判官の積極性が手続集中の鍵となることについての理解の齟齬が見受けられ、それがわが国における「適正・迅速かつ公正な裁判」実現の障害となっていることを明らかにした。そして、裁判官の積極性の観点からは、発問・指摘義務、当事者への出席命令、職権による文書提出命令などとの関連で当事者の真実義務を考慮する必要があること、そして、この真実義務は当事者の証拠調べ協力義務との関係が重要であり、当事者行為の失権を導き出す前提になるのではないかとの問題意識を持つに至った。その関係で、以下の三点を考察対象とした。一つは、訴訟における情報収集の局面での当事者の行為規律であり、とくに、この点では、情報提供がより可能であるが、証明責任を負わない当事者に対する二次的主張責任との関係から当事者の行為規律を考察する点である。この考察対象についてはドイツ法系での議論について主に研究対象とした。第二は、信義則による当事者の行為規律である。とくに、この点については、我が国における判例の展開を中心に考察・分析し、比較法的な考察を展開した。第三は、これら2つについての議論を真実義務の観点から分析・検討し、当事者の行為規律のあり方についての考察を深めることである。この観点では、真実義務自体についての再検討も比較法的考察に基づいて実施したきた。その結果、信義則についての判例の分析などはある程度進展し、一部研究成果を公表したが、二次的主張責任や真実義務については諸外国の実情を把握することが必要と感じ、2020年3月にドイツ法系諸国への海外視察を予定したが、コロナウイルスの影響で渡欧ができなくなった。実態調査に基づく分析、考察が今後の課題となっている。平成30年度の研究は、民事訴訟法制において真実義務導入や当事者行為の失権強化の先達となったオーストリア民訴法、母法国ドイツ民訴法及び最新のスイス 民訴法を中心に、この当事者規律をめぐる評価等に関する情報収集と整理を中心的に実施していくことを内容とした。令和元年度の研究は、この研究をベースに、①二次的主張責任、②信義則による当事者の行為規律及び③真実義務の観点からの①②の分析を研究課題として実施してきた。①については、とくに訴訟における情報収集の局面での当事者の行為規律について、情報提供がより可能であるが、証明責任を負わない当事者に対する二次的主張責任との関係から考察することを、ドイツ法での議論を中心に実施した。ドイツ法では、弁論主義の支配する「当事者の自己責任に基づく民事訴訟モデル」は当事者に情報収集手段がなく、訴訟上重要な事実を具体的に述べることができない場合には機能しないという前提の下、当事者間の協力義務が議論され、ドイツ民訴法138条1、2項、同277条1項、同282条1項及びドイツ民法242条に関する学説・判例が二次的主張責任の根拠付けで検討されていることがわかった。②については、信義則による当事者の行為規律をわが国における判例の展開を中心に考察・分析した。我が国では、信義則による当事者行為の規律が中心となっているが、その基準が必ずしも明確でないことを明らかにした。③において、これら2つについての議論を真実義務の観点から比較法的にドイツ法系諸国の研究者等との意見交換を通じて分析・検討し、当事者の行為規律のあり方についての考察を深めることを真目指したが、コロナウイルスの影響で渡欧ができなくなったため、課題として残っている今後の研究は、前年度の歴史的・比較法的研究の整理、分析に基づき、わが国民事訴訟法における当事者の行為規律のあり方を明らかにすることを目的とする。前年度及び前々年度においては、民事訴訟法制において真実義務導入や当事者行為の失権強化の先達となったオーストリア民訴法、母法国ドイツ民訴法及び最新のスイス 民訴法を中心に、この当事者規律をめぐる評価等に関する情報収集と整理を中心的に実施してきた。そして、具体的には、真実義務、二次的主張責任、そして信義則及び手続による当事者行為の失権という当事者行為規律に関する沿革的な議論と現在の状況に関する比較法的検討結果の整理、分析研究を引き続き実施し、わが国民事訴訟における当事者の行為規律のあり方について一定の取りまとめを行いたい。比較法的研究では、真実義務と二次的主張責任との関係、及びスイス法が採用した同時提出主義たるAktenschlussと真実義務についての研究を継続していく。今年度は、昨年度中コロナウイルスの影響で実行できなかったドイツ法系諸国の実態に関する調査を実施し、民事訴訟実務などを視察し、実務と理論の知見を得て、 前年度行った検討結果の検証と分析を行う。加えて、環境が整えば、英米法諸国の民事訴訟法制 における当事者規律に関する研究も上記と同様に行う予定である。また、このような比較法的研究・調査の整理・分析に基づき、わが国民事訴訟の実務改革、改正の変遷に関して、理論的検討と検証を実施していくが、その中でもその理論的側面についての考察を中心的に行っていきたい。とくに、現在ではほとんど議論されていない真実義務が、当事者の行為規律にどのようにかかわってくるのか、そして、「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」のために は、これらの関係をいかに規律すべきかを実務的観点から分析し、理論的側面の検討・検証していく予定である
-
民事訴訟における「手続集中」理念とその諸方策に関する研究
研究期間:
2015年10月-2018年03月概要を見る
本研究は、民事訴訟における「適正・迅速かつ公正な裁判」の実現はなぜ「手続集中」に委ねられたのか、その根源(一八九五年のオーストリア民訴法)に遡り、現在に至る変遷を明らかにし、わが国におけるこの実現に関する将来の展望を試みたものである。そして、本研究では、「手続集中」理念がわが国大正民訴法改正に大きな影響を与え、現行民訴法に受け継がれていることを明らかにし、手続集中のための方策の重点は上訴まで含めた審理システムの構築と訴訟主体(裁判官・当事者)の行為規律との組み合わせにあり、とりわけ、裁判官の積極性が手続集中の鍵となる旨主張し、「弁論主義」の存在意義に関する批判的検討を展開した。この研究では理論と実務の架橋をめざし、根源、沿革、複眼という三つの観点から考察した。つまり、研究対象(手続集中理念)について、その生成及び本来の意味は何であったかといった根源を探求した。そして、その沿革を探り、その対象の変遷とその理由・背景とを追求した。そのうえで、その研究対象の現在的意義を、類似物や諸外国のそれと比較しつつ、地域性、社会性、経済性など多面的・複眼的視点から探求した。これらの考察に基づき、現在の民事訴訟実務における研究対象の現実的検証を試みたものである。こうした研究は法律学と法律実務間の連動・関係性を考察するモデルを提供し、かつ裁判実務及び立法にも寄与するものと考える
-
科学研究費助成事業(明治学院大学) 科学研究費助成事業(基盤研究(C))
研究期間:
2007年-2008年山本 研, 松村 和徳, 木川 裕一郎, 畑 宏樹, 村田 典子, 草鹿 晋一
概要を見る
倒産手続における担保権の処遇につき、(1)担保権消滅請求制度、(2)商事留置権の処遇、(3)担保権実行の中止命令、(4)リース契約の処遇、(5)流動集合動産譲渡担保権の処遇という5つのテーマを取り上げ、比較法的検討、あるいは、手続横断的検討という観点に配慮しつつ、旧法下および新法下の判例・学説、さらには、立法段階における議論等を参照し、6名の研究者による議論を通じた検討を行い、一定の解釈論的見解を示すに至った。
-
控訴審改革に関する比較法的研究-控訴制限、弁論更新権を中心に-
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2005年-2006年松村 和徳, 大濱 しのぶ, 草鹿 晋一, 畑 宏樹
概要を見る
本研究は、ドイツ法、オーストリア法、フランス法、アメリカ法における控訴審改革の詳細を、統計資料や裁判実務の実態などを調査して、分析・検討し、その上で、わが国の控訴審の実態を調査し、理論的考察を行うこと目的とした。昨年度実施した控訴審実務についての聞き取り調査に基づき、比較法的観点から分析を行った。その結果について、実際に審理を行っている控訴審裁判官と議論し、控訴審改革の方向性とその点に関する比較法的研究を重点的に実施した。本研究において抽出した控訴審改革について具体的かつ重要ポイントとは、以下の三つである。まず、(1)控訴審における控訴受理(理由)のあり方である。(2)控訴審における審理のあり方である。ここでは(1)第1回結審の実質、問題点、(2)争点整理の方法、とくに、控訴審における新たな主張の取扱い、時期に遅れた攻撃防御方法の処理などについて随時提出主義から適時提出主義への転換を考慮して、検討した。(3)控訴審における釈明のあり方、とくに現実には事後審的運用がなされている控訴審での釈明のあり方について分析・検討を加え、(4)人証調べについて必要性の吟味も含め、分析、検討した。第三に、(3)(1)、(2)を前提としたうえでの続審制の再検討である。共同研究の結論としては、続審制を維持したうえでの事前手続の導入などを考慮した柔軟な審理が望ましいが、控訴審改革は、既判力基準時との関係、裁判所の釈明義務との関係、再審制度との関係、上告審との関係などを考慮したうえで実行すべきことになる。わが国の近時の改正が、第1審集中化という方向性をもってなされたこと自体は問題ないが、それが、他制度との連関性の中で実施されたと思われない点が問題である。控訴審改革を通して、第1審から上告、再審までの制度設計を考える。こうした検討結果については、岡山大学法科大学院紀要「臨床法務研究」第4号に掲載予定である
-
統計による民事司法制度の国際比較-データに基づく司法政策研究のための基礎作業として
科学研究費助成事業(岡山大学) 科学研究費助成事業(基盤研究(C))
研究期間:
2002年-2003年松村 和徳, 我妻 学, 町村 泰貴, 菅原 郁夫, 山田 文, 飯塚 重男
概要を見る
本研究は、各国の司法統計、とくに事件件数、新受、既済事件数、判決、和解数・割合、平均審理期間、事件類型別の事件件数等、上訴率、法曹育成制度、ADRなどについて、各国を比較し、そのデータを分析して、とりわけ、わが国との対比から、わが国司法改革にどのような示唆を与えうるかなどを検討することを目的とした。
各国の司法統計は、そのデータの保存に対する意識の差異からか、データ収集方法、項目についてかなりの違いがあり、一般的にわが国の司法統計と比較することは難しいが、特定の項目においては比較検討が有効である。例えば、控訴審における統計では、とくにドイツなどは近年の改正(2001年改正)の原因(手続の遅延、破棄・変更率の高さ)を統計データから読み取ることが可能であり、わが国の控訴審改革にとって一定の指針を与えるものと思われる。イギリスの統計データも司法改革との関連で分析すると興味深い。
人口比率などからみてわが国の裁判事件数が他の諸国と比較して極端に少ないことが読み取れる。その原因が国民性なのか、それとも他の原因があるのか、今回の分析データからは明らかにできなかったが、これからの課題でもある。また、新受件数と既済件数との関連など、単独のデータからではなく、裁判所の人的・物的設備からの総合的分析などが必要なことがわかり、この課題についても同様の分析の必要性がある。さらには、司法統計データは、その国々の社会・経済情勢との相関関係をぬきにしては語れず、そのデータの推移の背景を知ることが重要であり、それらの分析もわが国司法改革にとって不可欠のものであることが明らかになった。 -
地域的リーガルネットワーク構築に関する総合的研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2000年-2003年中村 誠, 松村 和徳, 服部 高宏, 守屋 明, 佐藤 五郎, 山田 文, 佐野 寛, 田頭 章一
概要を見る
地域における法的サービスのネットワーク化の今日的特徴として、そのネットワーク化の部分性、非公式性、任意性を挙げることができる。しかし、法的サービスの質的高度化を図るためには、総合的な法的サービスのネットワーク化を通じてはじめて、各法律専門職はその自らの役割を十全に果たすことができるという視角が必要である。法的サービスのあり方を考察するため、法的サービスの提供者・利用者の相互連携のための包括的リーガル・ネットワークのモデルを構想した。このようなリーガル・ネットワークの中で、各種法律専門職間の相互連携が果たしうる機能は、相互理解と情報交流を活発化させ、市民や企業からの複合的な法的サービスへの期待に対する応答力を高めることである。法律家のネットワーク化を通じた法的サービスの高度化を図るためには、市民ないし企業により期待される法的サービスに法律専門職がどのように連携して応えるかという視点のみならず、むしろ法律家連携を通じて従来の法律家分業の中では受け止めることのできなかった市民ないし企業の潜在的期待を如何にして掘り起こし、顕在化させ、またこれを当事者の利益に結びつけていくかという、一層積極的な複合的サービスへの視点が必要とされる。リーガル・ネットワークの中での大学の役割は、各種の法律専門職や行政・市民団体等から提供される情報を様々な角度から分析し、その問題性に対して幅広い、長期的視点からの提言を行うなど、二次的に加工された情報を提供する機関として意義づけられる
-
第三者異議の訴えの異議事由拡張過程に関する研究
概要を見る
今年度の研究は、第三者異議事由の拡張過程とそこでの一般的基準の解明を目的とした研究に従事した。この研究で特に注目したのは、所有権を中心とした物権的請求権を異議事由としてきた第三者異議の訴えが、債権的請求権をその異議事由とするに至った異議事由の拡張過程であった。これまでの研究で明らかとなったのは、次のことである。まずこの過程では、近世初頭の経済的取引の飛躍的発展に伴う商品所有権の地域的に広範な流動という背景が存在した。そこでは、所有権と債権的返還請求権とは分離されることが頻繁に生じ、その結果、所有権についての証明軽減または所有権移転の中間に属する者に執行救済を得させるために、実務上、債権的請求権を有するにすぎない者にも第三者異議の訴えの原告適格が認められるに至り、それは今日的意味における訴訟担当の形により行われた。そして、債権的請求権は物権的請求権と競合しうる取戻請求権(Herausgabeanspruch)と交付をもとめるにすぎない交付請求権(Verschaffungsanspruch)とに分けられ、前者についてのみ第三者異議の訴えが許容された。しかし、その後、後者についても第三者異議の訴えは拡張された。ドイツでは、破産否認権に基づく返還請求権-Verschaffungsanspruch-が異議事由として認められた。この背後には、否認状況における執行排除の必要性という具体的妥当生重視の思考が存在した(もっとも、1990年のBGHの判例はこれまでの判例を変更し、否定説をとり、非難されている)。また、わが国では、こうした権利から出発する思考だけでは第三者異議事由の範囲としては狭いと考え、戦後以降、第三者と債権者との関係における実体的違法性による思考傾向が強まり、平成5年3月4日静岡地裁浜松支部判決はこの思考から債権的請求権一般につき第三者異議の訴えを認める。この結果は、現在執筆中であり、これまでの研究もあわせ論文集にまとめる予定である