【数理科学デジタルオープンレクチャーズ】
現在,世界中のさまざまな大学においてオープンコースウェアが行われています。 そのような中で、数学・数理科学専用の OCW があっても良いと思い、個人の活動としてではありますが、大学・大学院レベルの数学・数理科学に関するオリジナル講義動画を作成し公開しました。さまざまなコースがありますので、ご覧ください。
URL: http://www.araiweb.matrix.jp/OpenLect.html
【NEWS】NHK総合「世界!オモシロ学者 スゴ動画祭5」(2023年3月16日放映)にビデオ出演しました.研究成果の一つであるオリジナル錯視も紹介されました.
【オンライン教育教材の新作公開】数学者が書いた深層学習,畳み込みニューラルネット篇,MATLABプログラム付き.(2025年1月6日)詳しくはこちら.
研究活動等:
【特許・研究シーズ】(多数の特許を取得。取得特許については下記サイトをご覧ください。)
早稲田大学特許・研究シーズ『視知覚の数理科学とその産業応用、特に各種画像処理技術、錯視、商用アートへの展開』
【著書】(いずれも単著)
新井仁之「フーリエ解析とウェーブレット」(朝倉書店,2022年)総頁数 250+x
新井仁之「これからの微分積分」(日本評論社,2019年)総頁数 362 +v
新井仁之「有理型関数」(共立出版,2018年)総頁数 170+ix
新井仁之「正則関数」(共立出版,2018年)総頁数 183+ix
新井仁之「錯視のひみつにせまる本」第3巻「錯視と科学」(ミネルヴァ書房,2013年)(中国語訳あり)
新井仁之「ウェーブレット」(共立出版,2010),総頁数 463+xi
新井仁之「新・フーリエ解析と関数解析学」(培風館,2010),総頁数 339+viii
新井仁之「線形代数 基礎と応用」(日本評論社,2006),総頁数 537+x
新井仁之「微分積分の世界」(日本評論社,2006),197+x
新井仁之「フーリエ解析学」(朝倉書店,2003),総頁数 277+vi
新井仁之「ルベーグ積分講義 - ルベーグ積分と面積0の不思議な図形たち」(日本評論社,2003),総頁数 333+viii
【NEWS】
第10回 Waseda e-Teaching Award を受賞しました(2022/2).詳しくはこちら

朝日新聞(2018年11月24日朝刊)で錯視と画像処理の研究成果が取り上げられました。
第7回藤原洋数理科学賞大賞(2018年9月)を受賞しました。詳しくはこちら。
米国科学雑誌 『Nautilus』 のサイトで視覚・錯視と画像処理の研究成果が取り上げられ紹介されました.詳しくはこちら.
これまでの新聞報道等はこちらをご覧ください.
【主な受賞歴(受賞年順)】
2018年9月
藤原洋数理科学賞大賞
授賞理由:数理視覚科学と非線形画像処理の新展開
受賞者:新井仁之
受賞のことば(日本数学会編『数学通信』2019年2月号より)
2013年9月
日本応用数理学会 日本応用数理学会論文賞 (JJIAM部門)
論文名「Framelet analysis of some geometrical illusions.」
受賞者:新井仁之、新井しのぶ
詳しくはこちら(日本応用数理学会HPより)
2008年4月
文部科学省 文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)
受賞理由:視覚と錯視の数学的新理論の研究
受賞者:新井仁之
新井仁之氏の受賞によせて(日本数学会編『数学通信』13巻3号より)
1997年3月
日本数学会 日本数学会賞春季賞
受賞理由:複素解析と調和解析の研究
受賞者:新井仁之
詳しくはこちら(数学(岩波書店))
1995年8月
Featured Reviews
タイトル:Hitoshi Arai, Degenerate elliptic operators, Hardy spaces
and diffusions on strongly pseudoconvex domains, Tohoku Math. J. (1994),
pp.469-498. (95h:46034)
【説明】Featured Review は,Mathematical Reviews誌(アメリカ数学会)により世界中の数理系学術誌に掲載された論文からoutstanding paper として選ばれたものです.
詳しくはこちら.
その他の受賞もあります。
【自己紹介(履歴・研究歴)】
新井仁之 (Arai Hitoshi)
早稲田大学教育・総合科学学術院 教授
東京大学名誉教授
1959年横浜生まれ
[中高時代]
1972年に獨協中学・高等学校のドイツ語組に入学。中学1年からドイツ語を第一外国語として学びました。ここでドイツ語を初めて学び、とりわけドイツ語の文法の仕組みの美しさに感動し、ドイツ語文法を熱心に勉強していました。
しかし、中学2年の秋に獨協を退学、ドイツのボンにある Nicolaus Cusanus Gymnasium という中高一貫校に入学しました。そして約1年そこでドイツ語による教育を受けました。ドイツでは哲学、特に認識論に興味をもち、独学で哲学を学び始めました。
帰国後、再び獨協に中学3年の秋から編入学しました。中学3年のときにカントの『純粋理性批判』を読み始め、すっかり取憑かれてしまい、この哲学書に没頭しました。『純粋理性批判』は中学生の私にとって、人の認識を論理的に解き明かそうとする新しい壮大な世界でした。こういったこともあって中学・高校時代は、名誉校長で著名な哲学者の天野貞祐先生(日本で初めて純粋理性批判を完訳)、そしてとりわけ校長でかつて東京大学教授だったドイツ文学者の小池辰雄先生から薫陶を受け、哲学・認識論の勉学に専念しました。高校のときには認識論に関する論文を書いたりしていました(未発表)。
このほか、中学3年のときに数学担当の原田恒久先生のご指導の下、遠山啓著『微分と積分 その思想と方法』(日本評論社)を読みました。原田先生が数名の中学・高校生に対し放課後講義をされ,私もそれに加わっていました。講義は本の前半で終わりましたので,続きは一人で読みました。もともと数学そのものにはそれほど興味があった訳ではありませんが、大学の数学は中学の数学とは全くの別物で、それ自身新鮮で面白く、『微分と積分 その思想と方法』は大学レベルの数学への扉を開いてくれました。ただ当時は哲学・認識論への興味が強く、高校に進級すると結局哲学・認識論の勉学に専心しました。
それから数十年後、『微分と積分 その思想と方法』の新版がでるとき、出版社から解説を依頼され、新版には私の解説が載りました。現在,この本はちくま学芸文庫として出版されており,私の解説も掲載されています。
中学生の頃、まさか将来、読んでいるテキストの巻末に自分の解説が載ることになろうとは想像もしていませんでした。
【ギフテッド教育】
ところで、近年、日本でもギフテッドと呼ばれる生徒に対するギフテッド教育が注目されつつあります。文部科学省がギフテッドの教育の支援に乗り出したとの報道もありました。今から思えば、45年以上前に中学・高校で哲学や数学のギフテッド教育の一種かそれに類するものを受けていたと言えるのかもしれません(ただし私にはギフテッドと言われるような特別な才能はなく、ギフテッドではありません)。普通の教育も通常どおり受けていたので、ギフテッド教育との折衷型でした。
もちろん当時のことですから学校にギフテッド教育のシステムがあったわけではありません。それはきっちりとシステム化されたものではなく、教員が好意的に行なってくれた、柔軟性のあるカスタムメードのギフテッド教育であったと言えるでしょう。45年以上前の日本に於ける中学校・高等学校のギフテッド教育の一つの事例ではないかとも考えられます。
ギフテッドについて追記(2024)。
最近、ギフテッド教育の失敗事例やデメリットが報告されています。上記のものが今でいうギフテッド教育かどうかは不明です。というのは教育自体はギフテッド教育とも言えるかもしれませんが、私自身がギフテッドではないので、先生も特別な生徒への教育とは感じていなかったのではないかと推察されます。しかし、私自身にとってはカリキュラムにはない自分の興味あることを学べ、また小池辰雄先生など私のつたない話を一蹴せず聞いてくださり、アドバイスをしていただけるなど、とてもありがたいものでした。このときの認識論・哲学の勉強が、数十年後に始めた数理視覚科学を研究する(下記「大学教員時代」参照)下地の一つになっていることは確かです。結果的にはこのギフテッド教育はうまくいったと考えられます。
理想論を言えば、通常の授業では学べないことを学びたい生徒に、生徒の個々の諸状況に合わせたカスタムメードで教え、優れた能力の部分を育てられると良いわけです。ギフテッド教育については、2Eの問題や通常クラスでの疎外・いじめなどいろいろ課題が多いのですが、私が言うまでもなく、今後もあきらめずに様々な研究・実践を重ね、犠牲になる生徒を出さないように実施していくことが望ましいでしょう。
理想目標は「たまたま良い先生・環境に出会った」を「必要な場合に良い先生・環境に出会える」にすることです。ここでよい先生とは、生徒が興味をもった分野の専門知識をもち、ギフテッドに理解のある人を意味します。
[大学時代]
高校のときは哲学・認識論の勉強に明け暮れていましたが、大学では哲学を研究するために、まず数学を軸に自然系・人文系の勉強をし,それから哲学科に行き、哲学を専攻しようと思っていました。1978年に高校を卒業し、早稲田大学教育学部に進学しました。大学では数学者の和田淳藏先生の研究室で純粋数学(主に多変数複素解析の関数環への応用)を学びました。卒業論文はこの方面の最先端のことまでをまとめ、ささやかながらいくつかのオリジナルな結果も得ました。数学を勉強するうちに哲学から数学に興味が移り、1982 年に早稲田大学大学院理工学研究科数学専攻の修士課程に進学し、1984年に同博士課程に進みました。大学院では主にブラウン運動と調和解析の交錯領域の研究を行いました。
そして翌1985年には教育学部に数学の助手として戻ることになり、教育学部では教員として、理工学研究科では大学院生として過ごしました。
[大学教員時代]
1986 年に東北大学理学部の数学科の助手に招かれ、早稲田は中退。仙台に移住し、確率論と微分幾何学と多様体上の解析学の融合領域の研究を行いました。東北大学では猪狩惺教授の実解析セミナーに参加しました。その間、プリンストン大学数学科客員研究員(受け入れ教授はエリアス・スタイン先生)、東北大学理学部講師、東北大学大学院助教授を経て、37歳のとき
1996 年に東北大学大学院理学研究科の数学の教授となりました。
1999年に東京大学大学院数理科学研究科の教授に招かれ異動しました。
東京大学ではある切っ掛けで、脳内で行われる視知覚の情報処理のメカニズムや視覚が起こす錯覚(錯視)の研究を始めました。そして視知覚や錯覚を先端的数学、脳科学、神経科学、知覚心理学、コンピュータ・ビジョンなどを使って総合的に研究し、さらにその成果を実用的な技術に結晶化する新分野『数理視覚科学』を提唱、以来その研究を進めています。
数理視覚科学の研究により、これまでに世界で初めて
*幾何学的錯視の錯視量の自由な制御(新井・新井、2005)
*任意の画像の浮遊錯視画像への変換(新井・新井、特許取得、2012,)、
*スーパーハイブリッド画像(新井・新井、特許取得、2013)
*文字列傾斜錯視の自動生成(新井・新井、特許取得、2014)
*色の錯視の数理モデルによる解析(新井・新井、特許取得、2014)
*新しい画像処理方法(新井・新井、特許取得、2014)
*ディジタル・フィルタ群の新しい設計方法等(新井・新井、特許取得、2014)
などに成功しました。
2018年に母校の早稲田大学教育・総合科学学術院に移籍し、現在に至っております。
プロフィールは新井仁之の自己紹介から移植.
【オンライン教育サイト】
ルベーグ積分講義 講義動画集
新井仁之『ルベーグ積分講義(改訂版) 』(日本評論社,2023年)と連動した講義動画サイトです。
プログラミングしながら学ぶ応用線形代数と深層学習
数理科学オープンレクチャーズ
(数理科学,AI,錯視科学に関する独自のオープンコースウェアです.)

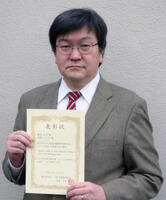

Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API in February 19, 2026, via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .