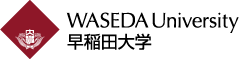特別研究期間制度(学内資金)
-
過疎法のもとでの小都市の地域活性化についての研究
2011年09月-2012年03月フランス他
2026/03/04 更新
基本情報
社会貢献活動・その他
2026/03/04 更新

過疎法のもとでの小都市の地域活性化についての研究
フランス他
2016年
概要を見る
2010年に「過疎地域自立促進特別措置法」が改正された際に、いわゆるソフト事業に対する過疎対策事業債の充当が明文化されたが、これは筆者の長年の主張でもあった。その後5年以上の年月が経過し、地域の活性化のために工夫されたソフト事業がかなり立案されるようになってきた。本研究では、市町村担当者からのヒアリングによって、岩手県遠野市、富山県南砺市、熊本県山江村、長崎県南島原市、鹿児島県伊佐市のソフト事業の実態を調査した。斬新なものとしては、みらい創りカレッジ推進(遠野)、結婚活動支援(南砺)、小中学校ICT整備(山江)、農林漁業体験民泊推進(南島原)、在宅当番医制支援(伊佐)などが注目された。
2015年
概要を見る
国の過疎対策事業として行われてきた、過疎地域活性化優良事例表彰の対象となった団体を選び、その後の展開過程の実態を調査することによって、過疎地域に活力を生み出す方策のヒントとすることが目的である。下川町では、森林の持続的経営のもとでバイオマスエネルギーの自給の集落が生まれ、関係NPOの活動も盛んになった。南さつま市のNPOは集落の支援を超えて、商業施設のない地区にサロン的な商店を開業し、弁当の配達も手がける。南九州市のNPOは、大学と提携した古民家のリフォームによって市街地の活性化に踏み出した。上島町の「しまの会社」は特産物の通販と交流がさらに充実している。表彰がばねになって進化していることが共通点である。
地域サポート人材の活用による過疎地域の活性化のための取組みの意義と成果
2015年
概要を見る
総務省が創設した地域おこし協力隊および類似の事業によって若者を受け入れ、定住につなげる試みが地域に活力をもたらしていると思われる3つの地域の実態調査を行った。兵庫県朝来市は10名の隊員の情報の共有と住民のサポート体制を重視し、岐阜県郡上市明宝地区では、3名の隊員が地元のNPOや活動団体に所属して、起業や事業の拡大にチャレンジしやすい体制をつくっている。大分県竹田市も、29名という多数の隊員を、市全体の組織の中に位置づけ、勤務日数を減らしていくなど、起業しやすい体制がとられている。いずれも、隊員に対する日常のサポート体制が強固であることが重要な特徴と考えられ、すでに地域に活力をもたらしている状況がある。
地域おこし協力隊の受け入れによる過疎農山村の活性化への取り組みとその意義
2014年
概要を見る
総務省の地方活性化事業である地域おこし協力隊の受け入れ地域から4地域を選び、活動の実態調査を実施した。協力隊員の配属には地区別の方式とテーマ設定によるものがあり、今回の調査地域では、島根県美郷町と鹿児島県薩摩川内市が地区別、島根県邑南町と長崎県対馬市がテーマ設定による例であった。小さな地区の生活支援的活動が多くを占めると活動のモチベーションが上がらないという話も聞かれ、これに対してテーマ的に活動する方が多くのキーパーソンとの接点が得られやすく、将来の定住への足掛かりをつかみやすいと考えられる。特に対馬市では、1期生が二つの法人をつくっており、大きな成果が見られた。
2014年
概要を見る
過疎地域活性化の取り組みについて表彰を受けた団体から5カ所についてフォローアップ調査を行った結果、次のような実態が明らかになった。①沖縄県南大東村では、アクセスの不安定さが改善されず、エコツーリズムの展開が滞っている。②徳島県美波町ではウミガメの保護・観察が続けられ、関係グッズの販売も進んでいる。③大分県(株)つえエーピーでは健康志向の産品開発に成功し、6次産業化が進んでいる。④大分県大山町農協は組合員農家の指示でさらに直販店を増やし、地元にとってなくてはならぬ企業となっている。⑤熊本県(財)学びやの里は、20年にわたる田舎ツーリズムの学習の場としてその使命を果たし終えようとしている。
過疎農山村におけるルーラルツーリズムの展開とその社会論的意義
2013年
概要を見る
農業の効率化や大きな企業の立地が困難な過疎農山村においては、小規模な農業と農家民宿などを組み合わせるツーリズム複合が重視されるべきことを、筆者は早くから指摘してきた。筆者は長く国の過疎地域に対する政策の在り方にかかわってきているが、本研究は、過疎農山村においてルーラルツーリズムがいい形で展開していると思われる事例の実態調査によって、その在り方を考える一助としようというものである。 当初の計画では、3か所の現地調査を行う予定であったが、沖縄県宮古島市において調査すべき事例が展開していることを知り、経費上の制約も勘案して、現地調査を熊本県水俣市と沖縄県宮古島市の2か所にすることに予定を変更した。 熊本県水俣市の久木野地区は、1956(昭和31)年に水俣市に合併した旧久木野村であり、97%が森林という山村である。合併当時は3,000人以上が住んでいたが、今は400余りの世帯に1,000人足らずの人が住み、高齢化も進んでいる。この山深い久木野地区に愛隣館という地域活性化の拠点施設があり、年間約15,000人が訪れていることは驚きである。大部屋の宿泊室もあり、イベントや体験、研修で、年間のべ300人程の宿泊者がいる。 この施設は、水俣中心部に通じていたJR山野線の廃止に伴い、地元で「久木野むらおこし研究会」が駅跡地の活用を市に要望した結果、1994年に市が建設し、現在「水俣市久木野地域振興会」(任意団体)が管理者となっている。この施設がユニークなのは、建設された1994年に館長を全国公募し、その運営を任せたことである。館長に選ばれた沢畑亨氏は東大農学部で修士を終了した俊秀で、農山村への思いが強く、この20年近く様々な事業やイベントを企画し、農山村の価値を世に発信してきた。その事業を列記する。・地元の食材を使った食品の販売、カフェレストランの営業、家庭料理の会の開催・ボランティアによる21haの森づくり、合宿・会費制の大豆畑耕作、棚田にたいまつを2,000本立てる「棚田のあかり」、棚田米の販売・2時間のむらづくり・森づくり研修、1泊2日の「棚田食育士」研修、2~3泊の実習 市の管理費、研修収入、食品の売り上げ、公的な補助金の導入などによってこれらの事業を遂行し、沢畑氏を含むスタッフ3人が地域に住んで、困難な拠点施設のいわば専業経営を20年間続けていることは特筆すべきことである。上記の事業が地域社会を元気にしていることは疑う余地がない。 沖縄県宮古島市は2005年に5つの市町村が合併して生まれたが、旧城辺(ぐすくべ)町では合併前に有志が「ぐすくべグリーンツーリズム研究会」を設立し、これが「ぐすくべグリーンツーリズムさるかの会」に発展して、翌2006年から大阪の府立高校の修学旅行生の受け入れ(農家民泊)を開始した。会の農家リーダーの松原敬子氏は農家にこの事業に参加することの価値を訴え、初年度から31戸の農家の協力を得て、260名の生徒を受け入れたことは驚きである。 島の農家の素朴で温かい対応が口コミで伝わり、2007年度には2校約400名、08年度は11校役3,000名、09年度は18校役5,500名、10年度は24校約6,300名、と増え続けた。2011年度は32校約9,500名、12年度は34校8,400名と驚異的な実績を示したが、13年度は市の観光協会がグリーンツーリズム事業に乗り出したこともあって、26校約6800名と少し減少に転じた。しかし短期間でこれだけの支持を確立していることは驚きである。 体験メニューは、農業体験、郷土料理体験、海などの自然体験、地域文化・郷土芸能の学習などであり、サトウキビの刈取りや三線の体験も含まれるが、農家民泊が単なる農業体験に終わるのではなく、農家まるごとの生活体験の中で都会にない「地域」を感じてもらうことを重視している。 本研究では、二つの違ったタイプのルーラルツーリズムの展開をとらえることができた。一つは水俣市久木野地区の愛隣館という、農山村への思いの強いエキスパートが常駐して外部の人を巻き込んだ事業の展開に成功してきたタイプであり、今一つは、地域の農家がツーリズムの価値に気づき、仲間をつくって、短期間のうちに都会の若者の受け入れを増やすことができたタイプである。ツーリズムによる過疎地域の活性化の事例のタイプはさらに多様であると思われるが、今回の二つのタイプはその中で基本的なものに位置づけられるであろう。そしてこの二つの事例ともに、相談事やお互いの役割分担が生まれ、地域社会そのものが活性化していることを確認できた。このテーマについては、次年度においてもさらに分析を重ねたい。
2003年
概要を見る
本研究は、一昨年度から昨年度にかけて科学研究費および特定課題研究費の助成を受けて実施した、「多自然居住地域の創造のための地域連携の実態調査と展望」の更なる発展として、現実に進んでいる市町村合併の状況の中での多自然居住地域の創造の可能性を検討しようというものである。今回は前年度に取り上げた4地域の中から特に熊本県阿蘇地域について現地ヒアリングを行った。 阿蘇地域(阿蘇郡)12町村は、当初県が阿蘇郡全体が一体となる合併案を提示したものの、これに対する支持はなく、4ないし5のグループに分かれる様相を見せた。その後の紆余曲折を経て、現在次のような展開を見せている。 阿蘇外輪山の中の北部は阿蘇地域の中心部ともいえる地域であるが、ここでは阿蘇町・一宮町に外輪山東側の産山村・波野村の協議会が作られ、現在産山村が離脱中である。外輪山の北部はかつて小国郷と呼ばれた小国町と南小国町の2町の協議会で検討中である。南郷谷と呼ばれる南部では、長陽村・久木野村・白水村が南阿蘇村を作ることに決している。ここはあえて村を名乗る。その東の高森町は合併しないで単独で歩む姿勢を強め、最も南の蘇陽町は南西部に隣接する清和村・矢部町との合併を選んだ。また外輪山の西側になる西原村は、熊本市をも含めて、西部平野部での合併の以降である。 これらの推移の状況には、住民とのやり取りを含む手続き上の問題がかかわっていると見られるが、それに加えて、住民の生活行動から浮かび上がってくる圏域のあり方を反映している面も強く見られる。産山村は昨年の調査で、病院・高級な消費財などの機能において、隣町を超えて熊本市の利用が目立っており、蘇陽町も、矢部町という阿蘇地域外の機能の利用が目立った。西原村にいたっては多くの機能を熊本市で充足しており、現在の市町村合併の動きは、古い時代の枠組みとは無関係に、住民の生活行動を反映するものになりつつあることが見出せた。
2002年
概要を見る
科学研究費によって、2ヵ年にわたって、4地域において、都市的な生活サポート機能の立地状況とその利用に関して、ヒアリング及び簡単なアンケート調査を行なった。いずれも県庁所在地ないしそれに準ずる中核都市から1時間以上の時間距離を要する地域である。このような地域で、オリジナルな地場の産業を育成しながら、レベルの高い都市的な生活サポート機能を享受できるしくみを作ろうというのが、多自然居住地域の創造という国土計画のテーマである。対象とした生活サポート機能は、病院(風邪等、要手術、出産、歯科)、買物(通常の食材、高級な食材、日常の衣料、外出用衣料)、外食、金融、旅行エージェント、書店、高校、自動車教習所、図書館等である。 この特定課題研究費によって、4地域のうち北海道富良野地域と岩手県遠野地域について追加調査を行い、研究をより充実させることができた。その結果の概況は次のとおりである。 富良野地域では、高レベルの機能になると、中核都市である旭川の利用が目立ち、旭川に近い上富良野町のみならず、遠い南富良野町にも旭川の利用が見られ、中核都市の利用が不可欠になってきている状況が窺われる。特に中核都市の利用が目立ったのは、重い病気の場合の入院先、高級な食材の購入、外食のレベルアップ、外出用衣料品の購入、パソコンの購入等である。 遠野地域では、遠野から見て花巻側にある宮守村・東和町に遠野市の機能を利用する人が格段に少なく、より上位の都市の利用が目立つ。これは花巻市の持つ機能のレベルが実際に遠野市よりも高いという価値判断と同時に、両町村から見て、花巻市が、盛岡市さらには東京というより上位の都市の方向にあるという心理的な効果があるやに思われる。 上に挙げたレベルの高い機能の利用に関しては、1時間ないしそれ以上の時間をかけて、中核都市まで出かけ、いわば全国的に見てレベルの劣らない機能を得ようという動きが顕著になっていることがわかった。これは全国の生活サポート機能が、地方中核都市レベルでかなり標準化してきていることを窺わせ、小都市の機能のレベルアップによって、余り広域的な移動を必要としない、レベルの高い生活圏の構築には、なお、新たな戦略が必要なことを意味している。
1999年
概要を見る
多自然居住地域とは、新しい全国総合開発計画である「21世紀の国土のグランドデザイン」において、成長する都市とは異なるタイプの発展を実現すべき地域として、中枢・中核都市から遠距離にある中小都市と農山村を想定してつくられた概念である。安易に人口増を望むのではなく、他の地域との連携の中で、土地や資源を従来にない取り組みで活用することにより、レベルの高い生活を樹立していくことがその眼目である。熊本市や福岡市から遠距離にある熊本県小国町は、その資源や自然を活用して、自らの地域をさまざまな交流の場として活用する仕組みをつくり、この時代をリードしてきたが、1997年から、新たに「九州ツーリズム大学」という取り組みを始めた。筆者はこの取り組みが、都市から遠い山村地域において地域がその価値を強力に発揮し、過去にはなかった山村の存在価値をつくり出す画期的な試みであると考え、その実態を調査した。 この「ツーリズム大学」には99年度までの3期で130人が学んだ。カリキュラムは9月に始まり、毎月1回、3日間の研修を受ける。これを運営するのは小国町北里地区につくられた「財団法人学びやの里」であり、宿泊とメインの研修場所は、以前から交流の拠点となってきた木魂館である。カリキュラムには調査・料理の実習もある。 参加者の居住地は熊本県のみならず九州北部全域に広がり、福岡市からの参加者も各期にいる。年を追うごとに、ツーリズムに無関係な都市の勤労者が増えてきている。氏らは、自らの人生の新たな可能性を探ることをここでの講座に求めていることが明らかになった。そして卒業生130人のうち28人が、すでに、農家民宿や農家レストランなどの、自然と資源を生かした事業を始めている。都市化に追随するのではなく、都市にたいして新たな役割を果たす多自然居住地域の創造の萌芽が、ここにはっきりと見られるといえる。
1998年
概要を見る
奈良県吉野郡川上村は、わが国で最も古くから大規模な育林事業が始まった場所の一つで、現在でも植林後200年を超える育成林が残り、再生産されている。しかしその林野は早くから村外へ流出し、外部の山林地主(山主)が村内の人(山守)に人工林の育成・管理を委託し、山守が労働者を組織して山主に利潤をもたらすという独特の林業が展開してきた。そして、現在の川上村は奥地山村の例にもれず過疎化が進行し、奥地の林業への若い世代の参入も次第にむずかしい状況になってきている。 本研究は、山林の所有者の多くが村外にいる状況の中で、林業において必ずしもイニシアチブを取りにくい行政当局が、それとは別にどんな発展の構図を描いているかを検証し、山村問題を考える指針の一つとしようというものである。 川上村は全国に存在する同名の町村と連携し、全国川上町村協議会を発足させた。これは一時流行した同名の自治体の交流事業であるが、その交流の中から、「川上」という河川の最上流に位置する地名の意味を積極的に考え、環境問題が普遍化しつつある現代社会に、<水源地の村>として、環境問題への問いかけをしつつ村づくりをしていく姿勢を共有する動きが生まれた。有識者を交えた担当者らの議論は、年に一回開催される川上町村サミットの場を、川上宣言の発表の場にするところまで進んだ。川上宣言は、河川の最上流に位置する町村が手を携えて、生命を育む自然の偉大さを語り、下流にきれいな水を流しつつ環境の意味を啓蒙しようというものである。 ちょうど川上村では建設省が治水を主目的とした多目的ダムを建設中であり、このダム建設の経緯の中でも、従来とは異なった対応が見られる。それは、水源地の村として、ダム建設は容認するものの、ダム建設が水源地の生活を破壊するものではなく、それをいかに発展の契機としていくかという発想である。現地調査に基づいてこれらの対応を整理しつつあり、後日あらためて発表したい。
1997年
概要を見る
わが国の農村社会は、他の国々に比べて高い生産力を持つ水田をいかに保持し続けるかという基本的原理で維持されてきた。山村においても早くから林業に特化した村は例外的で、厳しい条件の場所に水田を開いてきたことが一般的な歩みである。そして社会制度としてのその最も端的な現れは一子相続である。本研究は、水に恵まれない瀬戸内海の離島が、ある契機からミカン生産に特化した過程を調査研究し、その展開過程において、わが国一般の水田をベースにした農村社会の展開過程とは異なる特質を見い出そうとするものである。 対象とした広島県豊町(大崎下島)では、島民が明治期に温州みかんを導入し、島内の急斜面にミカン畑を造成し、水田を持つ農村とは全く異なった景観が生まれた。特に大長地区ではこの動きが顕著であり、ついには他の島々あるいは本土の海岸の森林となっていた斜面を購入してのミカン畑造成にまで進んだ。この結果、船でミカン畑に通うという特徴ある生活様式が生まれた。農耕船の数はピーク時より減ってはいるが、現在でも日本において際だった状況がここにある。 なぜこの地の人だけが、借金を重ねてまで他の島や本土にまで土地を求め、大変な労苦を重ねてミカン畑を増やしていったかという契機は今回の調査で必ずしも明らかにならなかったが、そのような行動をとった理由が、自分の子供たちができるだけ多くこの島で生活していけるようにしたいという願いに基づくものであったということを、何人かからのヒアリングで確かめることができた。このように、水田のように価値ある耕地を持たなかった地域の人々が、既存の枠内での一子相続という発想を持たずに行動したという、日本の農村社会を相対化できる事実を見出すことができた。
1995年
概要を見る
本研究の目的は,わが国の農山村が全体としては衰退の傾向にある中で,比較的発展的な様相を呈していると考えられる事例について,その基本的条件を整理検討することにある。研究対象としたのは,青森県相馬村と熊本県小国町である。 相馬村は,現在一人当たりリンゴ生産出荷額が日本一の自治体であり,農業そのものの発展的展開に成功している。また小国町は,山村の構造変化の時期に「悠木の里づくり」と題するソフト戦略を展開し,住民の意識改革から地域社会の発展的状況を作り出した。今回の現地調査から得られた知見は,次のように整理できる。 1. 相馬村は基本的には水田農村であったが,早い時期にまぐさ場をリンゴ園に転換したことに加え,もと入会林野であった暖斜面を購入することによって,農地に執着する東北農村の中で,比較的スムーズに経営面積を拡大することが可能になった。 2. リンゴ栽培は機械の導入が困難で労働力の投下量が多いにもかかわらず,現在相馬村においてある程度の大規模経営が成り立っているのは,弘前市から近く,臨時労働力として弘前市の主婦層などを雇用することが可能なためである。 3. このように発展的な取組が生まれてきたのは,中堅農家が集落を超えて連絡を取り合い,時代を先取りした展開ができたためである。 4. 小国町においては,地元産の杉を利用した斬新なデザインの建築を拠点とし,その建設の過程にかかわった人々が,従来の集落中心の人間関係にとらわれない新しい生き方を見いだした。 5. ある時期地域を支えた林業の体制を,革命的に変えて若者の職場とすることに成功した。 6. 集落を超える旧村単位の土地利用計画チームが,熱意のある若者の参加で活動を始めた。 以上の知見から考えられることは,新しい人が活躍できる農山村の実現のために,少なくとも集落の枠を超えた単位で地域社会を考えていくことの必要性である。
Copyright (C) 2020 WASEDA University, All Rights Reserved.