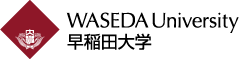特定課題制度(学内資金)
特定課題制度(学内資金)
-
ヘテロアトムの特性を活かしたチイルラジカルを経るバイオミメティック反応の開発
2003年 秋葉 欣哉
概要を見る
チイルラジカルは活性化されたC-H結合から水素引き抜きを起こすが、この反応は逆反応がはるかに速く、これはSH/CH結合エネルギーから考えて当然である。一方、炭素ラジカル(R・)によるSHからの水素引き抜き反応はR-Hが活性酸素などで傷ついた核酸、蛋白などの生体分子の“修復反応”として知られており、チオール種としてはcysteine残基が考えられている。ところがチイルラジカルによる水素引き抜きが鍵反応となる酵素反応として ribonucleotide reductase (RNR) の反応があり、これは熱力学的に不利な水素引き抜き過程で開始される反応として興味深い。上述したようにチイルラジカルによる水素引き抜き反応は不利な反応であるにもかかわらず、生成すすR・が逆反応に拮抗できる位の速度で他の化学種に変化して系から除かれればR-Hのチイルラジカルによる分子変換が可能になると考えて以下の研究を行った。 まず、中間体ラジカルが安定で逆反応が遅く、ピナコール生成が逆水素移動に拮抗する系としてBenzyl-OTBSエーテルのチイルラジカルによる水素引き抜き反応を行った。ここで、チイルラジカルはジスルフィド類の光開裂(で発生させた。(MeS)2の反応性が高く、芳香族ジスルフィドは反応性を示さなかった。注目されるのはC6F5S・の示す高い反応性である。この場合、ピナコール体のほかに、酸化生成物であるαーhydroxy体を与えることである。このことは次式の1電子移動過程が中間体ラジカルの有効な除去機構として働いていることを示している。 R・ + (R'S)2 → R(+) + R'S(-) + R'S・ つぎに、2-phenyl-1,3-dioxane類のチイルラジカルによる水素引き抜きを行った。ここで注目すべき点は4,4-dimethyl体から出発しても、5,5-dimethyl体から出発しても酸化生成物ω-oxipropylbenzoateが生成することである。 これら酸化物の生成はジスルフィドが酸化剤として働いていることを示している。酸化生成物の酸素源であるが、冷凍脱気を繰り返しても生成物に変化が見られず、積極的に溶媒を湿らすと酸化物の生成が促進されることから反応液中の水分子に由来することが分る。また、注目すべき点として5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3-dioxaneからは水素引き抜き生成物は全く生成せず、酸化体のみが生成することである。一方、メチルチイルラジカルによる4,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dioxaneからの水素引抜では水素引き抜き体である(3-methylbutyl)benzoateが主生成物となり、C6F5Sラジカルによる反応では酸化物が主生成物となる。すなわち、C6F5S・を用いた場合、ジスルフィドへの一電子移動(SET)が、(a) (MeS)2では遅く、(C6F5S)2では速い、(b) ラジカル中間体の開環よりもSETが速い、(c) 4,4-dimethyl体のラジカル開環速度は5,5-dimethyl体より早いと考えれば理解できる。これらのことからC6F5S・は有効な水素引き抜き剤であり、かつ(C6F5S)2は有効な電子受容体であることが分る. つぎにチイルラジカルに及ぼす水素結合の効果について検討した。(MeS)2を用いた4,4-dimethyldioxane体の反応系にCH3(CF3)2COH (A), (CF3)2CHOH (B), (CF3)2C(OH)2 (C)をそれぞれ添加してその効果をみた。その結果、ピナコールの生成に対してAは影響を与えず、B(0.5mol/l)の添加ではその収率は62.5%から27.6%へと減少し,Cの添加では大きな影響が現れ、0.5 mol/lの添加でピナコール体は全く生成しなくなった。一方、酸化物が主生成物となる(C6F5S)2を用いた反応ではCの添加によりその収率は44.2%(無添加)→60.5%(C,0.5 mol/l)と向上した。このことはCの水素結合がジスルフィドへのSET段階でも影響していることを示している。したがってCはチイルラジカルに水素結合してその水素引き抜きを阻害し、またジスルフィドへも水素結合し,その電子受容能を高めると考えられる。 以上纏めると、(a) チイルラジカルの水素引き抜き能は本質的には生成するS-H結合の強さに依存する、(b) 電子吸引性置換基をもつジスルフィドは有効な1電子受容体である、(c) 水素結合はチイルラジカルの水素引き抜き能を減少させ、ジスルフィドの電子受容性を高める。 このような観点から(C6F5S)2はチイルラジカル源としても電子受容体としても特異な存在であり、これを用いて新たな有機反応の発見が期待される。
-
イオウ中心ラジカルを活性種とする補酵素モデルの開発とラジカル触媒作用
2001年
概要を見る
遺伝子DNA合成に必須のribonucleotideからdeoxyribonucleotideの合成にはriboseの2位水酸基が還元される必要がある。この還元をつかさどるのがribonucleotide reductase(RDR)であるが、この反応の第一段階はRDRのcystein残基のチイルラジカルがriboseの3位の水素を引き抜くところから始まることが分かっている。この過程はC-HとS-Hの結合エネルーギーから考えると不利は反応である。つまり、この水素引き抜き反応がスムースに起こるためには、チイルラジカルの活性化かC-H結合の弱体化が必要である。 本研究はチイルラジカルの活性化にはどんな要素が重要かについて実験的に検証することである。ここではチイルラジカルの反応性に影響する要素として(1)イオウに結合した有機基の電子的性質、(2)2組の孤立電子対の水素結合などによる効果、(3)水素引き抜きの遷移状態で電気陰性基がアピカル位に配位し、イオウが超原子価状態を取ることによる活性化を検討した。 Riboseモデルとしてbenzyl-t-butyldimethylsilyl ether (BzOTDMS),benzyl-methyl ether (BzOMe),および2-phenyl-5,5-dimethyl-dioxolan (PhDOX)といずれもフェニル基とエーテル酸素で活性化された基質を水素源として用いた。結果は有機基としてπー電気陰性度の大きなpentafluorophenyl基>phenyl基>alkyl基の順に水素引き抜き能が大きかった。次にイオウの孤立電子対に水素結合できるtrifluoroethanol,1,1-di(trifluoromethyl)ethanol,hexafluoroacetone-hydrateを反応系中に添加するとこの順に水素引き抜きは阻害された。次に分子内に配位性を有するヘテロ原子を配したチイルラジカルによる水素引抜を検討した。phenylethylthioラジカルのphenyl部位を2-pyridinyl,2-quinolinyl,2-quinoxarinylに置き換え芳香族窒素の配位効果を見たが、影響は見られなかった。2-(1,1-di-trifluoromethyl-1-hydroxyethyl)benzenthiylラジカルがメチルラジカルの引抜き反応に大きな加速効果を示すことから判断してイオウの超原子価状態による遷移状態の安定化には芳香族窒素よりも電気陰性度の大きな酸素原子が必要なことがわかる。 以上、酵素反応で重要な働きをするイオウラジカルの活性化に必要な要素を明らかにすることができた。
-
補酵素Mによるメチル基転移過程におけるイオウ超原子価状態の影響
2000年
概要を見る
メタン菌によるメタン発生の最終2段階はチオール基を有する補酵素M(HO3SCH2CH2SH)が関与する反応である。われわれは有機化学的に類形の無いこれらの反応を、基質・補酵素をすべて簡単なモデル系に置き換えてシミュレーションすることに成功した。このモデル反応においてはB12補酵素を簡単なコバルト錯体であるコバルト-(salen) (1)で、また補酵素Mを2-(2-hydroxy-perfluoroisopropyl)-thiophenol(2)でモデル化した。 モデル化合物1と2からは化合物2のチオールラヂカルが発生することが分かっている。モデル化合物2は大きな置換基を有するにもかかわらず、他のオルト置換チオフェノール類に比べてはるかに高い反応性を示した。この効果は電気陰性度の高い酸素のイオウラジカルへの配位効果以外では説明できず、この様なイオウの超原子価状態がラジカル反応性を高める効果を明らかにした始めての例である。イオウはこの遷移状態では(3-S-10)と表記できる両三角錐形の超原子価状態にあると考えている。 一方、メタン発生の最終段階はメチル化補酵素と補酵素HTPラジカルから混合ジスルフィド、(補酵素M)S-S(HTP)、とメタンが発生する過程であるが。補酵素Mのモデルとしてメチル化された化合物2を用いると、この反応は抑制された。すなわち、ここで分子内配位性基(OH)が配位した超原子価状態はすでに(3-S-10)状態を取っており、これにさらにイオウラジカルが相互作用するとイオウは(4-S-11)という電子配置となり不安定化すると考えられる。 このように補酵素Mの化学的性質を考えるとき、反応中心であるイオウの超原子価状態がその反応性に大きな影響を及ぼすことを明らかにすることが出来た。
-
1999年
概要を見る
トリフェニルスズコバロキシムはスズーコバルト間にシグマ結合を有する特異な有機金属化合物である。この金属間結合はきわめて弱く、熱や光照射によって容易に解裂してスズラジカルおよびコバロキシムラジカルを与える。ここで生成したスズラジカルはハロゲン化物からアルキルラジカルを発生させたり、アセチレン結合に付加して、ビニルラジカルを発生させることが出来る。これらのラジカル種は反応系中にコバルトラジカルと共存しており、その影響を受けることが考えられる。 本研究ではトリフェニルスズコバロキシムを4-オキサー6-エンー1-イン、4-トシルアザー6-エンー1-イン、5-オキサー7-エンー1-イン、5,7-ヂオキサー1-オクチン等と反応させ、中間に生成するビニルラジカルがどのような反応挙動を示すかを検討した。反応様式は光反応と熱反応では異なり、光照射条件下では中間体ビニルラジカルはさらに分子内オレフィンに対してタンデム環化反応を起こし、コバロキシムラジカルによる水素引き抜きによって環化したオレフィンを与えた一方、熱反応下ではアセチレンの末端水素がトリフェニルスズ基で置換された生成物のみが得られ、ラジカル環化反応はまったく見られなかった。 反応機構について検討した結果、光反応がトリフェニルスズラジカルの付加によって起こるのに対して、熱反応はコバロキシムからエンーイン類への一電子移動を伴って起こることが明らかとなった。これはコバロキシムの低い酸化電位に基づくものと考えられ、スズーコバルト混合金属錯体の特異な性質として興味深いものである。
-
1998年
概要を見る
酸塩基触媒作用の例に従えば、ラジカル触媒作用とはラジカル種が基質に配位して基質分子内に不対電子密度を発生し、その反応性を変化させることと定義できる。トリフェニルスズコバロキシムを光分解すると、スズラジカルとコバロキシムラジカルに解裂する。このスズラジカルがアルキルハロゲン化物と反応してアルキルラジカルを発生するが、この時系中にはコバルト(Ⅱ)ラジカルが共存している。アルキルラジカルが分子内にイオウ基を含んでいる場合、これがコバロキシムに配位する結果、(1)コバルト上の不対電子密度がイオウ上に非局在化してイオウ上に不対電子密度を生じ、(2)またイオウ基がビニルスルフィドの場合、不対電子はさらにビニル基上にも分布する。我々は(1)、(2)それぞれについてこれらに対応する反応例を発見して、それらをラジカル触媒作用と名づけた。 (1) チオエステル類存在下メチルコバロキスムを光分解すると、イオウ上でラジカル置換反応を起こしてメチルスルフィドが生成するが、この反応はコバロキシム不在下では著しい反応性の低下が見られる。 (2) 6-(ω-ハロゲノアルキルチオ)-ウラシルにトリフェニルスズラジカルを作用させるとアルキルラジカルがオルト置換した生成物とイプソ付加して生成するSmiles転移生成物が得られる。この際、系中にコバロキシムラジカルを共存させるとオルト置換が優先し、コバルト不在下ではSmiles転移が優先的に起こる。 これらの発見はいずれも上に示したラジカル触媒作用の好例である。
-
C<SUB>1</SUB>-単位転移に関与するコバルト・ニッケル錯体補酵素のモデル化
1996年
概要を見る
メタン発酵過程におけるメチル-補酵素Mの生成や、多くの生物群に見られる普遍的メチル基源 としてのメチオニン生成過程において、葉酸やメタノプリテリンの5位の窒素に結合したメチル基がコバルト錯体である補酵素B12の関与のもとに補酵素-Mやホモシステインに転移する。この転移反応をモデル化すべく、テトラヒドロプテリン類やアニリン類のメチル誘導体にアルキルチオーコバルト錯体を反応させた。その結果、メチル基は効果よく窒素からイオウ上に転移した。この際、チオールコバルト錯体としてパラ置換フェルチオコバオキシムを用いてい研究し、その酸化電位やX-線構造解析と反応性との関連を検討し、コバルト錯体からメチルアンモニウムイオンへの電子移動反応とそれに続くラジカル的分子置換反応が起こっていることを明らかにした。 メタン菌によるメタン発生過程では、上に記したN→S転移に続いてメチル基はさらにニッケル錯体であるF430に転移してメタンを発生すると考えられている。その際、メチル化補酵素-Mはメチル基を失って、さらにもう一つの補因子である(HTP)SHと反応して(補酵素M)S-S-(HTP)の混合ヂスルフィドを生成する。この過程をモデル化すべく、チオアニソールとトリルチオーニッケル錯体の混合物を光分解してトリルチオラジカルを発生させたところ、(フェニル)S-S(トリル)の混合ジスルフィドの生成とともにメタンの発生が認められた。 このように、反応機構的に全く未知の生化学反応に有機化学の面から新しい可能性を示唆する知見を得ることができた。この成果は生化学反応を規範として新しい有機化学反応を発見するという本研究の目的を充分に達成したものといえる。
-
1995年
概要を見る
C1-単位(-CHO,-CH2OH,CH3)の分子間転移反応はアミノ酸,核酸,メタン,酢酸等の生合成に関っており,特にDNA合成における核酸塩基ウラシルからチミンへの変換を制御することによる制ガン性との関連において葉酸の働きが注目されている。また,核酸合成とは別にホモンスティンや補酵素Mのチオール基に転移したメチル基は生体内でのメチル基源として各種の生合成反応において重要な働きをしている。 本研究では上記2点の過程に関わる補酵素である葉酸,メタノプテリンの類縁体を合成し,生体内反応をモデル化すること,および補酵素B12からイオウ化合物へのメチル基転移に関与するほ酵素類縁体を合成し,生体内反応をモデル化することを目的とした。 補酵素葉酸はプテリジン骨格を有しており,その骨格合成を行った。2-アミノ-3-ニトロソウラシルにホスゲン三量体を作用させて得られるジアジノンは各種電子供与性オレフィンと反応して,高収率でプテリジン類を与えることを発見した。この反応は一般性が高く,オレフィンとしてエナミン類,エノールシリルエーテル類と高い反応性を示した。また,反応の位置選択性も高く,6-位置換体のみを与えた。この反応を利用して6-位にアニリノメチル置換基を有する葉酸類縁体の合成に成功した。 次に補酵素B12のモデル化合物としてメチルコバロキシムを選び,この化合物からチオエステル類,ジスルフィト類のイオウへのメチル基移動を検討した。この際メチルコバロキシムの下方配位子を,立体容積の異なる配位子(ホスフィン類),電子的性質の異なる配位子(パラ置換ピリジン類)と変えてその反応性を調べた。その結果,チオエステルとジスルフィドは異なる機構でメチルラジカルを受け取っていることが分った。 この様にメチル基転移に関わる補酵素群の合成と反応機構の解明において重要な知見を得ることが出来た。