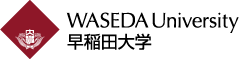共同研究・競争的資金等の研究課題
-
バイオチャーを用いた森林における炭素隔離効果と生態系応答機構の解明
研究期間:
2015年04月-2019年03月 -
森林生態系における土壌炭素放出に対する根圏滲出物の量的寄与と環境応答特性の解明
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2015年04月-2018年03月小泉 博, 友常 満利, 本多 朝陽, 棚澤 由実菜, 鞠子 茂, 村岡 裕由
-
陸上生態系の炭素シンク能力における長期持続性の検証
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2007年-2010年鞠子 茂, 小泉 博, 横沢 正幸, 大塚 俊之, 田村 憲司, 上條 隆志, 廣田 充
-
流域スケールでの土壌圏炭素シーケストレーション機能の評価
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2003年-2006年小泉 博, 秋山 侃, 鞠子 茂, 大塚 俊之, 別宮 有紀子, 横沢 正幸
-
高緯度北極域陸上生態系における炭素循環の時空間的変動の機構解明と将来予測
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2003年-2006年中坪 孝之, 神田 啓史, 小泉 博, 大塚 俊之, 村岡 裕由, 内田 雅己
-
樹木バイオマス相対成長式の統合と生態系純生産量の試算
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2003年-2005年小見山 章, 小泉 博, 加藤 正吾
-
生態系温暖化ポテンシャルによる生態系の温暖化影響力の総合評価
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2003年-2005年鞠子 茂, 小泉 博, 戸田 任重, 関川 清広, 杉田 幹夫
-
青海・チベット草原生態系における炭素循環のプロセスとメカニズムの解明
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2001年-2004年唐 艶鴻, 小泉 博, 鞠子 茂, 関川 清広
-
森林の破壊と再生に伴う炭素シーケストレーション機能の評価
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2000年-2002年小泉 博, 川島 博之, 小見山 章, 秋山 侃, 鞠子 茂
-
農林地および草原の持続的生産性評価のための指標作成
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
1999年-2002年秋山 侃, 板野 志郎, 篠田 成郎, 小泉 博, 塩見 正衛
-
木曽三川のエコロジカル流域管理計画
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
1999年-2001年秋山 侃, 小見山 章, 篠田 成郎, 小泉 博, 藤原 道郎, 中川 一, 宮坂 聡
-
各種陸上生態系における炭素・水・熱フラックスの相互関係の微気象生態学的解析
-
新たな土壌呼吸速度モデルの開発を目指した生理生態学的研究
-
森林・草原生態系の群落構造と相互作用機構およびその時間変動性の解明
-
小型MRI装置による森林土壌の非破壊計測研究のための技術的基礎の確立