共同研究・競争的資金等の研究課題
共同研究・競争的資金等の研究課題
-
グローバル・コモンズを巡る中国による国際法形成に関する動態的研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業
研究期間:
2017年04月-2020年03月池島 大策
概要を見る
英文書評(1) ‘Book Review Issues Decisive for China’s Rise or Fall: An International Law Perspective. By Yuwa Wei. Singapore: Springer. 2019. Pp. xxv + 203.’, Transcommunication Vol. 7-1, spring 2020, pp. 49-51. と英文書評(2) ‘Book review Normative Readings of the Belt and Road Initiative: Road to New Paradigms. Eds by Wenhua Shan, Kimmo Nuotio and Kangle Zhang. Springer. 2018.’, Waseda Global Forum, No. 16, 2019, pp. 133-137. を執筆した。これらの中で、国際社会における中国の台頭がその一帯一路政策を通じて国際法の形成過程や関係諸国の発展に関与し、一定の影響を及ぼしつつある現実について、時代の変化や国際社会の動態的な性格の顕現として捉えるべきである旨、論評した。以上の結果、(1)現行国際法を維持しようとする米国をリーダーとする他の先進諸国陣営側からは、中国が南シナ海や北極海のような海洋への自国権益の主張拡大を試みることで現状への挑戦・変更を模索するかのように見えること、(2)こうした米中対立が海洋のみならず、宇宙空間での開発(衛星発射、デブリの処遇など) の分野や軍事競争の拡大と見られていること、さらには(3)サイバー空間での国家による管理・規制の度合いに対する法規制の諸問題(表現の自由に代表される人権の問題、知る権利と軍事情報の秘匿性の問題、他国への干渉や妨害等の行為の取締りなど)につき、米欧のような自由主義諸国と中国のような権威主義的中央集権諸国との対立が一層顕著になっていること、が特徴といえる
-
近隣関係諸国に対する日本の海洋法政策とその戦略的意義
概要を見る
この3年間の研究により、課題に関する大幅な解明に向けて有意義な進展が見られたといえる。途中経過でもあるが、平均して毎年一本の学術論文及び学術報告・発表に加え、各種研究会での発表・報告と報告書作成など行い、所期の目標を達成することもできた。近時の進展が早い法現象のせいなどでさらに時間を必要とする個所もあるとはいえ、この研究成果を土台に、数年内により体系的かつ包括的な著作に仕上げることを目標に、これからの研究を進めることができそうである
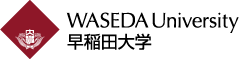

Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API in March 12, 2026, via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .